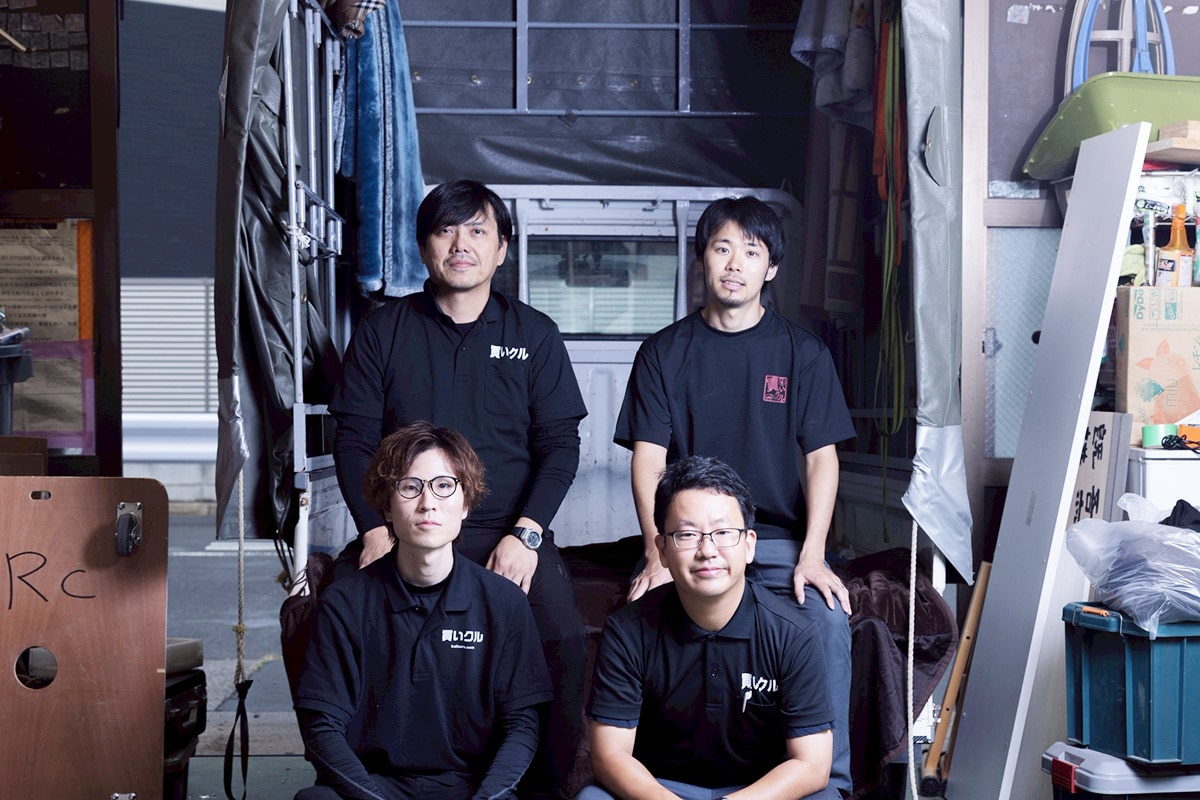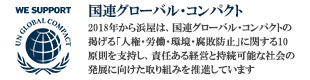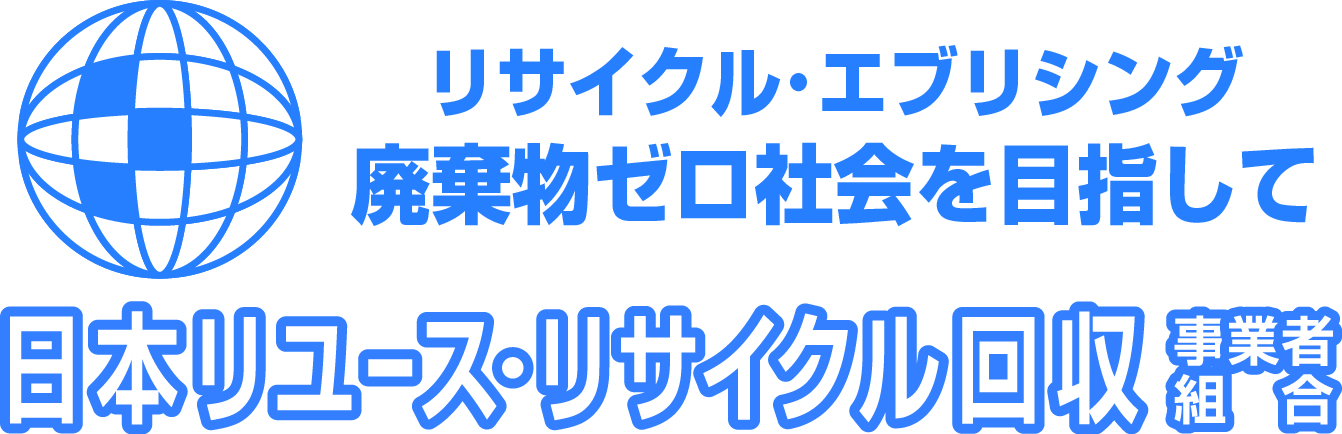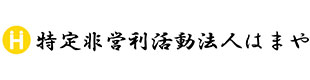世界初の“木の酒”を目指す!森林総合研究所主任研究員 大塚祐一郎氏【後編】

森林総研の大塚氏のチームが開発した、世界初の“木の酒”。前編では、主に造り方や開発までの苦悩を聞いたが、今回はいよいよ商品化した場合の展開などを聞いた。
地域材を使用すれば、その地域ごとの新たな名産品となり、地域活性化になり得るというーー。
前編はコチラ
世界初の“木の酒”を目指す!森林総合研究所主任研究員 大塚祐一郎氏【前編】
長かった緊急事態宣言がようやく解除され、多くの飲食店や居酒屋で酒の提供が再開された。仕事帰りの飲み会
長かった緊急事態宣言がようやく解除され、
今後は、さまざまな種類の木材での酒作りに挑戦
すでに開発したスギ、サクラ、白樺、水楢、クロモジといった樹種は、現在、安全確認のために動物試験を行っている。これらはすでに何かしらの用途で口に入れることが多かった樹木たちで、安全性は極めて高いと考えられるという。例えば、白樺はつまようじや割りばし、サクラは燻製スモークのチップ、水楢はウィスキーやワインの貯蔵用の樽に使用、クロモジは料亭の高級つまようじなどに使用されている。
今年度中には、ある程度の安全検査を進める予定だ。今後は、この技術を使って木の酒を造りたいという酒造メーカーを募集する。手を挙げたメーカーには、“木の酒”を造るためのノウハウを森林総研から学び、その後製品化してもらう流れを想定している。「すでにいくつかのメーカー様とお話はさせていただいています。このまま順調にいけば、早くて2023年頃には製品として発売できるのではないかと期待しています」。
また、新商品の開発も活発的に行っていく。例えば、酵母は、日本酒用、ワイン用とパン用は使っているが、今後は森で採れるようなものを試していきたいという。大塚氏は「当然、“木の酒”に合った酵母は現状ないわけです。もしかすると、自然界に木の酒に合う酵母があるかもしれません。例えば、サクラからも酵母がとれるので、その酵母をつかってサクラの“木の酒”を造ったらどうなるんだろうといった構想などがあります」と話す。
原料となる木材については、さらに研究を重ね、使用する樹種を増やしていきたいという。大塚氏は「フルーツの木やカエデなども試していきたいです。カエデの木から造った蒸留酒にメープルシロップ(カエデの木から作られる)を入れて、甘いメープルリキュールとかも造ってみたいですね。ほかにも、梅酒を造る際に、それを梅の木からできた蒸留酒のなかに、梅の実を漬けて作ると、正真正銘、梅しか使っていない“純度100%”の梅酒ができちゃうかもしれないです(笑)。サクラでもソメイヨシノや山桜、エドヒガンといった品種を変えて造って、利き酒などを行うのも面白いかもしれない。一つの樹種から一つの木の酒といういわゆる“シングルウッド”だけでなく、さまざまな樹種から造った木の酒を混ぜて作る、いわゆる“ブレンディッドウッド”として、オリジナルフレーバーなども造れると思います」と今後の構想を語ってくれた。

また、アルコール度数を強めた蒸留酒に醸造酒を少量混ぜて、香りを補填するなども考えている。「醸造酒は少し飲みにくいのですが色合いや香りは非常によく出ているので、その部分を蒸留酒に混ぜてあげるとさらによくなるのではないかなと思います。リキュールやスピリッツのような」。
「全国の産地で作った木材・樹齢ごとの“木の酒”を用意したウッドバーも将来的に開けたら面白いかなと思いますね」
時間のストーリーといった付加価値を
樹齢もほかの酒に比べて一つの強みになる。木は、一人前になるのに60年~100年などの年月が必要だ。例えば、赤ワインだと15年や20年ものになると高級酒。ウィスキーだとさらに顕著で、年数が上がっていくにしたがって、価格も上がっていく。サントリーが2020年6月に発売した「山崎55年」は300万円(税別)という販売価格だ。
“時間”という付加価値について、大塚氏は「木というのは、樹齢というストーリーがあります。木を切ると、年輪がありますが、中心から毎年外側に増えていきます。これは、経てきた時間が刻まれていっているんですね。もし、70年の木を切って酒にすると、それだけでもう70年ものになります。100年の樹齢の白樺を切って100本の白樺蒸留酒を造って、それを1-100とナンバリングするだけでプレミアがつくのではないでしょうか」と話す。
また、オーダーメイドの“木の酒”や、イベントでの用途などさまざまな付加価値も付けられると大塚氏は話す。
「記念でもいいですよね。例えば、長年住んでいた家を取り壊すとなった際に、大黒柱から“木の酒”を造るといったオーダーメイド的な展開もあるでしょうし、それを取っておいて、子供の成人式の時に一緒に飲むといったイベントでの活用も考えられます」
「季節で分けても味わい深いですね、桜は春に飲んで、夏は涼し気な白樺、秋はカエデ、クリスマスの時はモミの木の酒を飲むなども、新しいイベントの一環になりそうです。また、鳥居などを交換するとき、その古い鳥居で造るなど、神社仏閣に生えている御神木を使っての酒造りも考えられます。例えば、2010年に静岡八幡宮で大銀杏が倒れてしまいましたが、その使い道は限られてしまっていますね。これを“木の酒”にすれば、樹齢1000年ものの酒が出来上がります。本当の意味でのお神酒になるのではないでしょうか」
また、「筑波山で採れたスギや山桜、白神山地で採られた木、吉野杉や、パワースポットにある木で造った酒などもブランドがつけられると思います」と大塚氏。
これには、製品化した際の戦略的な面も透けて見えてくる。当然、初めて作るとなると、ビーズミルといった通常の酒造りでは使用しない設備投資を行い、人件費も大いにかかる。その資金を回収する必要があり、また今後の流通を考えると最初は高級酒で売り出した方がいいと大塚氏は考える。「最初から安く販売してしまうと、それ以上の価格に上げていくのが難しいですよね。そのため、最初は樹齢のプレミア感や、その土地のブランドなどの付加価値をつけて、高級酒として販売してもらいたい」と思いを語った。
最終的には、地域活性化を目指す
そして、この“木の酒”によって、最終的に目指すのは「地域活性化」だ。大塚氏は「森林総研のミッションは、研究の力で日本の林業を盛り上げていくことにあります。その土地にある木材で“木の酒”ができると、それがブランドとなり新たな名産品になります。そうすることで、木の価値観が飛躍的にあがり、その地方にお金が還元されることで、地域活性化につながるのではと考えています」と力を込める。

その言葉通り、“木の酒”の造り方については、森林総研単体で特許を取得しているが、造りたい民間企業がいれば自由に情報として提供していく。民間企業に特許を取得させなかったのは、一部の企業による技術の「囲い込み」を防ぐためだ。
さらに大塚氏は、「木の酒が造られ、普通に流通していく世の中になれば、木を見る価値観が今と異なっていくと思います。今までは、風景の一部でしかなかった木に対して、『この香りはいい』、『これ美味しそうだね』といった感想も増えていく。そのように木材の魅力がより一層高まれば、木自体の価値が見直され、木の酒だけでなく、木材を使った家具や道具といったものにまで世間の目が向けられ、木材産業全体が活性化していけるのではと期待しています」と話す。
海外の酒造メーカーから問い合わせがあっても、技術ノウハウの提供は、当面、断るとしている。その意図として大塚氏は、「世界初となる“木の酒”ですので、どうしても日本で最初に商品化していただきたい。日本の林業のために行っていることなので、ほかの国で先んじて作られてしまうとなんの意味もなくなってしまいます。日本の酒造メーカーの方にしか、まずは酒造りの情報提供は行わない方針です」と力強い口調で語ってくれた。
大塚 祐一郎(おおつか・ゆういちろう)
1977年、熊本県出身。博士(農学)。2004年東京農工大学大学院博士後期課程終了後、東京慈恵会医科大学研究員、2007年12月森林総合研究所入所。木材成分の微生物代謝、代謝工学技術による木材成分からの有用物質生産技術開発、木材の前処理技術開発に従事。2013年10月〜2014年9月バージニア工科大学客員研究員(併任)。現在に至る。