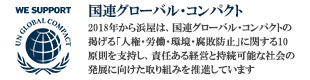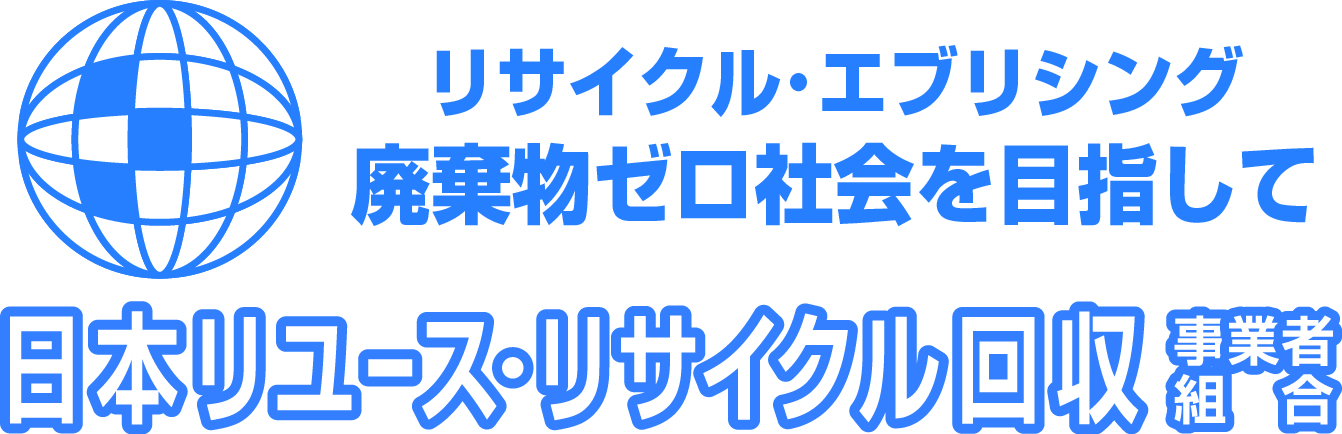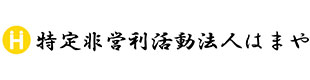環境産業の職場探訪① 大熊裕紀さん(26歳)アフリカにこだわり続ける

新年を迎え、大学生のみなさんで新たに就職活動を始めた人もいることでしょう。あるいは活動真っ最中の人もいるかもしれません。 どんな就職先を選ぶかと考えて、「環境」に関わる仕事につきたいと考える人も多いかもしれません。
そこでリユース業に携わる浜屋(本社・埼玉県東松山市)で働く3人の社員にインタビューし、生い立ちから、どうしてこの会社を選んだのか、入ってどんな仕事をしているのかを尋ねてみました。
「環境産業」といってもいろいろありますが、浜屋は、消費者や家電量販店などで不要になった家電製品や日用品などを調達し、国内や国外のリユース店に販売している会社です。ごみ問題の解決のためには3R(リデュース、リユース、リサイクル)が重要だと言われますが、そのリユース(再使用)を担っている会社です。
途上国の業者との取引が多く、海外志向の若者たちが多数働いている若い会社でもあります。 3人に小さい頃のことや、高校・学生時代の体験を伺うと、なんとなくいまの環境をキーワードにした業種に落ち着いたことが納得できました。 その過程でいろんな悩みもあったことでしょう。包み隠さず、率直に語ってくれた3人の体験記を読んだ方たちも、何かの参考になるかもしれません。
ジャーナリスト 杉本裕明
「アフリカと対等の視線に立ってやれる仕事がしたかった」。大熊裕紀さん(26歳)は、統轄本部の海外営業課でアフリカとアジア地域を受け持ち、相手国のバイヤーとの交渉に忙しい。千葉県生まれの大熊さんが途上国に目を向けたのは中学生の頃。「ユニセフの公共広告とか、クラスの担任の先生が、途上国で起きていることをいろいろ話してくれて。正義感からか、貧困とか差別の問題に対して、私も何かしないといけないのではないかと」。その想いが今の仕事に結びつく原点になった。
「ハンナのかばん」に衝撃を受ける
その頃読んだ一冊の本が大熊さんの記憶に強く残る。「ハンナのかばん」(カレン・レビン著、石岡史子訳)。
アウシュビッツの収容所で約100万人のユダヤ人が虐殺されたが、13歳だったハンナ・ブレディもそのひとり。ホロコーストを伝えるNPO法人を運営する石岡さんが、教材に使おうと、アウシュビッツの博物館からユダヤ人の残したかばんを送ってもらった。
表に「ハンナ」と記されていたことから、石岡さんは、ハンナの親族の消息を知ろうと動き始めた。やがてカナダに兄が生存していることを突き止める。こうしたかばんの系譜をたどりながら物語が進行する。「家庭でよき父親であった普通の人が、なぜ、残忍なホロコーストに手を染めたのか。人間はそこまでなれるのか。このようなことが起きない仕組みをもたないといけないと思った」
高校3年生の時、東洋大学国際地域学部には途上国でフィールドワークができる制度があると知った。迷わず選んだ。
途上国とのかかわり方に疑問が膨らむ
2年生の夏休みにフィリピンに1週間滞在し、教会が運営する孤児院で、子どもたちと遊んだり、ご飯づくりを手伝ったりした。ごみを拾う子どもで知られるスモーキー・マウンテンを訪問し、そこで暮らす子どもたちにごみ分別を教えてあげたいと思った。でも、すぐに違うとわかった。「教会の孤児もスモーキー・マウンテンの子も、自分たちが可哀そうな存在で、援助してもらう存在だと思ってはいなかった。それは先進国の上から目線の傲慢な考えだと気がついたのです」
3年生の夏にウガンダの農村へ。社会調査の質問票をつくり、現地の人々に質問した。JICA(国際協力事業団)出身の教授から、相手に教えていただいているという姿勢で聞くことの大切さを教えられた。4年生の夏には友人とバングラデシュで、ジェンダーの問題を考えた。 こうした経験を重ねるうち、これまでの自分の考え方に疑問を持つようになった。ボランティア、NGO活動が一方的な支援となり、途上国の支援を受ける側を援助慣れさせ、人として貶める存在にしてしまっていないか。「やはり、相手の国や人々と対等につきあえる関係でないといけない、そんな仕事に就きたいと思いました」
アフリカが自分の性に合っていると感じた大熊さんは、アフリカをキーワードに就職活動を開始した。アフリカの成長性を重視し、ビジネス拠点にしようとしている会社はたくさん見つかった。しかし、説明会では違和感を覚えることもあったという。ある会社は学生を一列に並べ、「ひとり3分で自己アピールしなさい」。ちょっと違うんじゃないか。
浜屋の説明会に行くと、社長が言った。「人は潜在意識の中で相手を喜ばせようと仕事をしている。お客に喜んでもらうことをやるんだ」。相手国の人と自分を同じ位置に置いて話していると感じた。それは、途上国を訪れ、「むしろ途上国の人々から教えられることの方がはるかに多かった」という大熊さんの気持ちとぴったり合うものだったから。
交渉し、契約取り付けた喜び
2015年4月に入社し、配属された海外営業課は課長以下6人。輸出国を地域割りし、それぞれの国のバイヤーから注文を受ける。大熊さんは、ナイジェリアなどアフリカ諸国、ベトナム、カンボジア、マレーシア、インドネシア。営業課の机が並ぶフロアに行くと、きびきびと英語で交渉している大熊さんの声が聞こえる。
相手国への輸出は、大きなコンテナに中古家電を詰める。注文を受けて内容を組み、確定するとコンテナ費用を送ってもらい、船積みの手続きを行う。本店や支店でコンテナに中古品を積み込み、港にトレーラーで運び、船に乗せる。 相手国の港ではバイヤーが入国の手続きを行い、会社でコンテナから取り出すと、中古家電店などに販売するという流れだ。
値段の交渉も行う。バイヤーの中には浜屋が幾らで仕入れているか知っている人もいる。浜屋はバイヤーへの売値を上げた場合には、必ず仕入れ値も上げている。これが良い品質のリユース品を仕入れるための浜屋の鉄則だという。「だから、『うちはちょっと苦しいが、その値段で我慢するよ』と言ってくれた時は、本当にうれしい」
こんな物が売れないかと、提案することもある。現地のバイヤーを先輩社員と訪ねることも多い。ナイジェリアに行った時は、オーディオ製品が並ぶ商店街を見て回り、新たにどんな商品を置いてもらえるだろうかと考えた。新たな商品開発が彼女の課題だ。
大熊さんは「同世代の友人女性のうち卒業して3年で3分の1が転職した。彼女たちに理由を聞くと、『その会社にいなければならない理由がなくなったから』。自分が何をやりたいのか、それに答えてくれる職場かどうかが大切だと思いました」と話している。