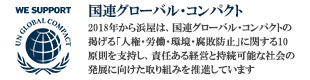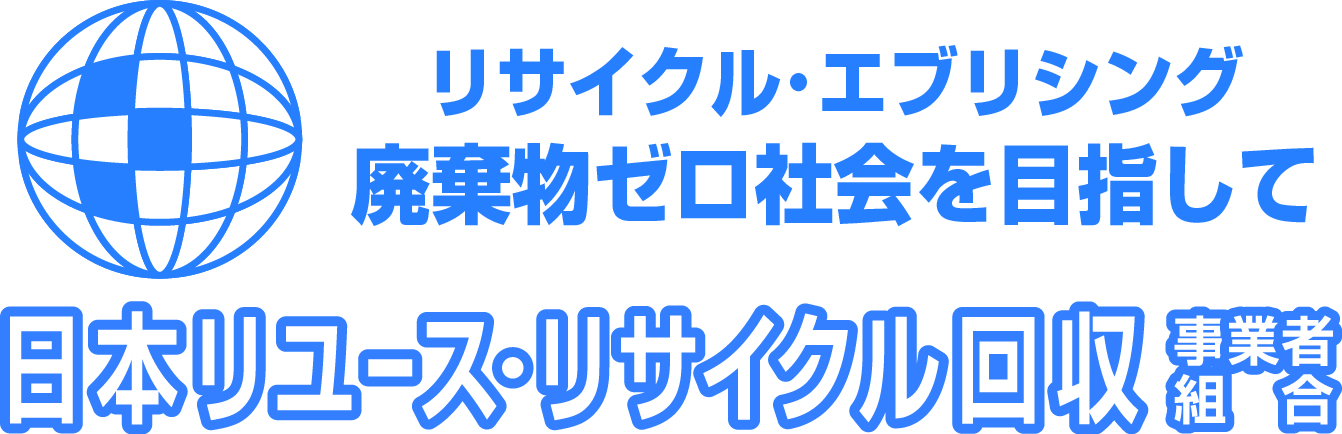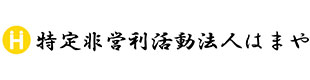小説からコロナウイルスを考える カミュの『ペスト』(新潮文庫)と篠田節子の『夏の厄災』(文春文庫)

新型コロナウイルスが猛威をふるっています。感染症の一つですが、世界的にはペスト、日本では日本脳炎が知られます。感染症をテーマにした小説も数多くありますが、ペストはカミュの『ペスト』(新潮文庫)、日本脳炎は篠田節子の『夏の厄災』(文春文庫)が有名です。
カミュの『ペスト』は1947年の出版で、カフカの『変身』と並び、不条理の世界を描いた小説として知られ、いまも読者を魅了し続けています。『夏の厄災』は組織と個人、組織と組織の制約の中で立ち向かう主人公らの動きが迫力を持って描かれています。中でも厚生省の怠慢ぶりは現実の世界を思い起こさせます。
いずれも中規模な都市で起きた事件設定ですが、『ペスト』はネズミの大量死、『夏の厄災』は軟体動物のオカモノアラガイが大量発生し、いずれもそれが媒介して人が感染するストーリーになっています。感染症の簡単な歴史とともに両書についてざっと紹介しましょう。
ジャーナリスト 杉本裕明
カミュの『ペスト』(新潮文庫)
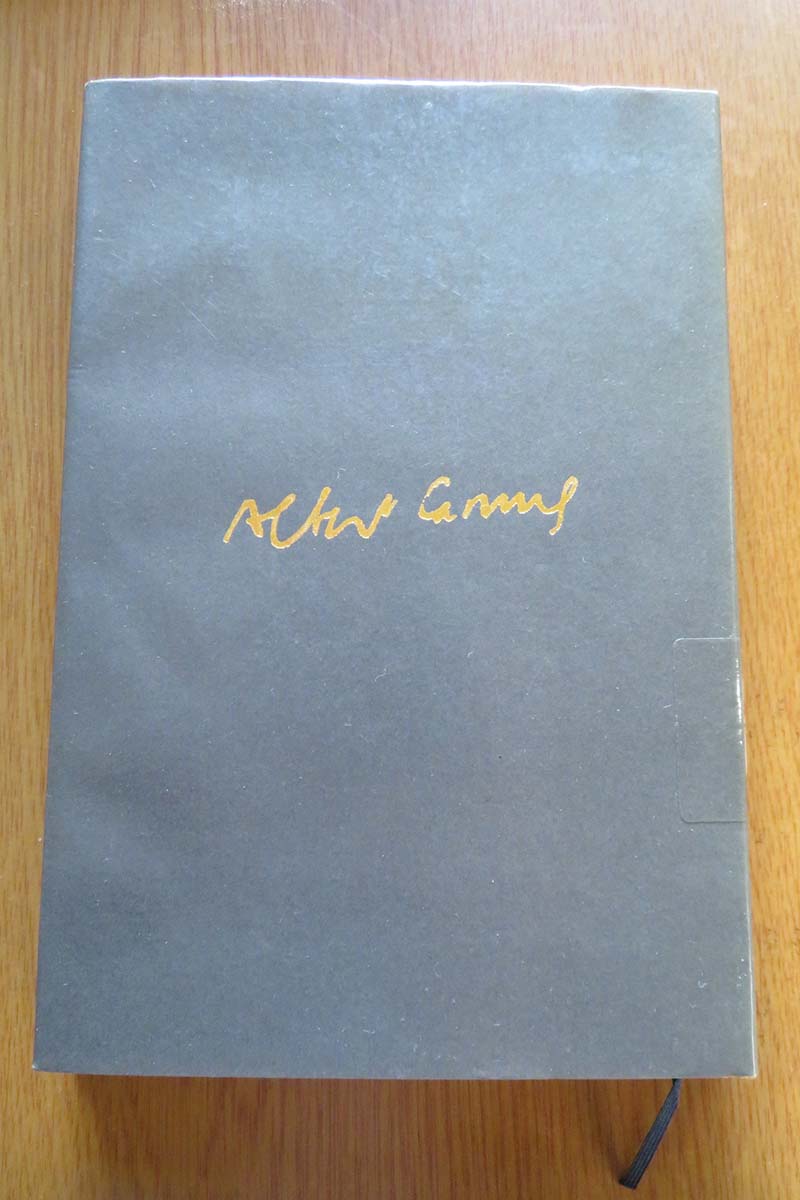
杉本裕明氏撮影 転載禁止
この小説の舞台は、当時フランスの植民地だったアルジェリアのオランという海岸沿いの小さな町です。この平穏な町が迎えた春。ネズミの死骸が見つかり、間もなく熱病が人々の間に広がり始めました。主人公の医師リウーはペストと疑うが、確証はありません。知事は平静を装い、県庁は白いビラを貼りだしました。
〈悪性の熱病の若干例がオラン市区に発生した。これらの症例は、実際に不安を感じさせるほどには献茶名特徴を示していないし、市民が冷静を保つうるであろうことは疑いを入れない。規定通り性格に理解され、実行されれば、これらの措置は流行病のあらゆる脅威をたちどころに阻止しうるていのものであるーー〉
主人公の医師、リウーは知事に電話をかけ、いまの措置では不十分だと訴えました。知事はペストだと認めたくない。が、それでもペストの時に行う患者の出た家を閉鎖し、家族は隔離され措置がとられ、わずかの血清が送られました。
しかし、死亡者が30人に達した時、知事は市の閉鎖を命じました。現在の中国・武漢と同様の措置です。
リウーいわく。
〈ペストがわが市民にもたらした最初のものは、つまり追放の状態であった〉
〈まさにこの追放感こそ、われわれの心に常住宿されていたあの空虚であり、あの明確な感情の動きーー過去にさかのぼり、あるいは逆に時間の歩みを早めようとする不条理な願いであり、あの突き刺すような追憶の矢であった〉
店が閉まり、海に出ることも禁止され、病原菌を焼き尽くそうと、自宅に放火する事件が頻発します。リウーは医者としてボランティアの保健隊を組織し、予防活動に懸命でした。
そして自説を訴える新聞記者にこう語りました。
〈『これだけはぜひいっておきたいんですがね。これは誠実さの問題なんです。こんな考え方はあるいは笑われるかもしれませんが、しかしペストと闘う唯一の方法は、誠実さということです』〉新聞記者が『どういうことです、誠実さっていうのは?』と尋ねると、『僕の場合には、つまり自分の職責を果たすことだと心得ています』
感動した新聞記者は一緒に働くことを申し出ます。 夏になり、ペストはピークを迎え、墓地に埋葬できる余裕がなくなっていきます。人々の心も変化していくのです。
〈ペストの初めのころには、彼らは自分の手元から失われた者のことを、きわめてよく思い出して、なつかしがったものであった。しかし、愛するその顔や、その笑い声や、今になってそれは幸福な日だったとわかった、ある日のことなどは、あざやかに思い出せたとしても、彼らがそうして思い出しているその時刻に、しかもそれ以来実に遠いところとなった場所で、相手がどんなことをしているのか、それを想像することが困難だった〉
〈ペストの第二段階においては、彼らは記憶も失ってしまった〉
やがてあんなに見られたネズミの死骸が一匹も発見されなくなりました。感染がおさまったのです。それを祝い、公式祝賀が行われました。花火が打ち上げられます。
最後にカミュは、リウーがこれからこの物語を書こうと考えたと記しています。なぜならそれが読まれることを知っていたからといいます。
〈ペスト菌はーー部屋や穴蔵やトランクやハンカチや反古のなかに、しんぼう強く待ち続けていて、そしておそらくはいつか、人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠(ネズミ)どもを呼びさまし、どこかの幸福な年に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうということを〉
篠田節子の『夏の厄災』(文春文庫)
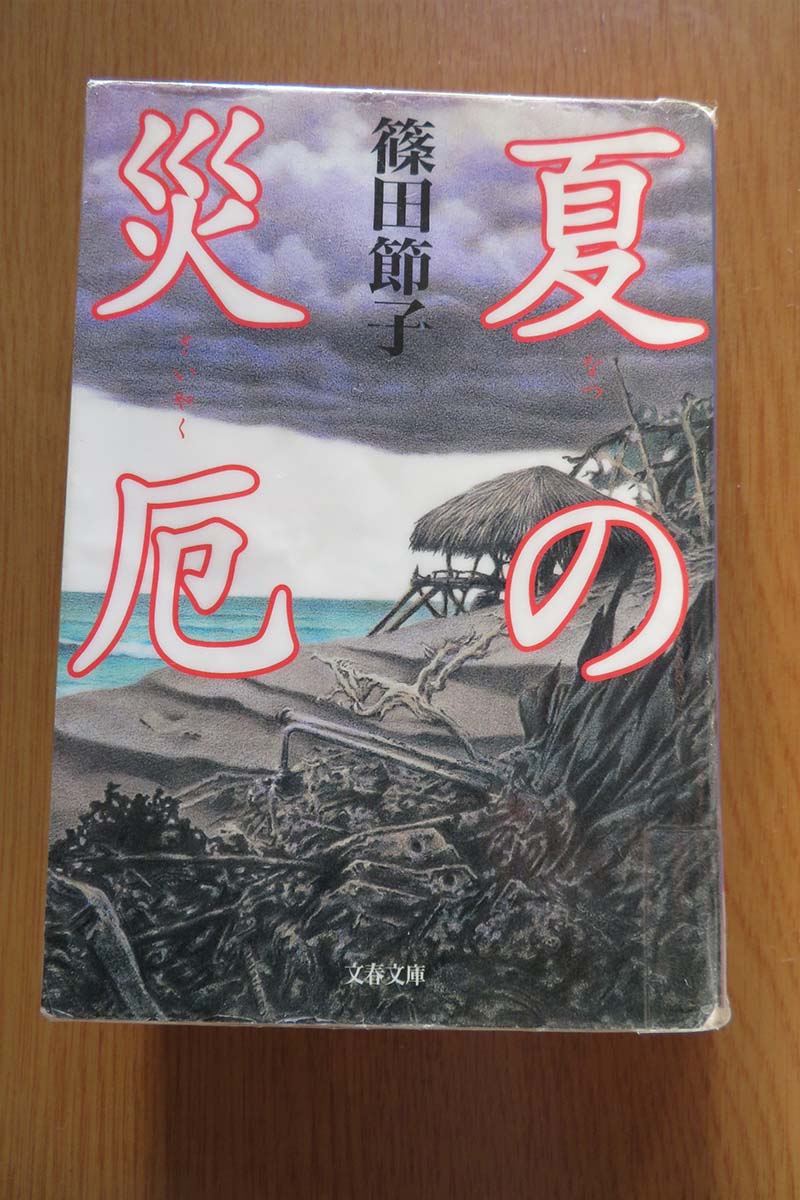
杉本裕明氏撮影 転載禁止
1995年の作品である『夏の厄災』は埼玉県昭川市(架空)で、新種の「日本脳炎」の発生と蔓延、その顛末を描いた小説です。昭川市の地図がついており、埼玉県東松山市が該当すると指摘されています。
人口8万6,000人の小さな市で謎の病気にかかり住民が亡くなっていきます。パニックに陥った住民たち。国の対応は「一地方都市で起きたことだ」と、そっけないものでした。
市保健センターの小西と看護師の房代が感染源を突き止める重要な役割を担い、それをきっかけに外国の製薬会社からワクチンが提供され、困難から脱するという筋書きです。
現在直面するコロナウイルスの「事件」と比べてみて、納得する記述が幾つもあります。
さまざまな噂が一人歩きする状況ーー。
〈あそこに行くとうつる。うつったら最後、簡単に死ぬ恐ろしい病気だ。これが市民のイメージする窪山地区の『日本脳炎』なのである。市民の間ではやがて窪山、若葉台の住民は感染者だ、という噂が広がり、窪山、若葉台地区の住民から 『その病気』がうつる、という内容に発展した〉
〈いったん情報が歪曲し始めると、後は水によって土が掘られ水路ができるように、さらに不正確さを増し、事実と大きくかけ離れていく。そして今度は、その歪曲した情報を裏付けしようとするように、それなりに筋の通ったいくつかの説が出てくる〉
ウイルス対策が所管のはずの国の対応は徹底して批判的に描かれています。当時、国の対応が批判されたエイズ事件が影響しているのかもしれません。
この新型ウイルスは、ごくわずかのウイルスに感染した人間の血液を吸った蚊から別の人間に移ることがわかり、間もなく「県内発生件数が58件、死亡者22人」に達します。
しかし、危険性と対策の必要性を必死で訴えた県のベテラン係長の永井に、厚生省のエリート官僚は、内心驚きながらもこう答えました。
〈『新型ということはわかりました。ただし現段階では、基本的な対応は特に従来と変える必要はないと思いますね』
『はーー』
『ですから、現段階ではですね』
若手官僚は繰り返した。何度聞いても同じ。国としては特に対策を立てないということだ〉
新聞も不正確な内容を記事にし、不安をあおり立てます。ある研究者の投稿を掲載しますが、それはアメリカ国防総省の生物戦争防衛計画の一部に日本脳炎ウイルスがあり、それが、国立予防研究所と関係があり、その研究員が、昭川市の大学病院に勤務している。研究所から大学病院に新田がウイルスの研究が移され、その地域に集中して新型脳炎が発生しているというものでした。 この小説ではこの事実は否定され、発生源探しは振り出しに戻るのですが。
50人目の死者が出ました。市は県を通じて厚生省に委員会の設置を依頼します。伝染病予防法でなく、新種の病気として独自の法令をつくって対処してほしいと。
しかし、ここでも厚生省は及び腰です。
〈『答えはすこぶる素っ気ないものだった。死者の数は多いが、発生は埼玉県どころか、ほとんど昭川市内に限られている。病気そのものは伝染病予防法に規定された日本脳炎と変わりなく、エイズのように新たな法令を作るには当たらない』こんな調子で、国の無策が描かれていきます。
ただし、学術協力については、実施の方向で検討しているという。
『一応考えてるんじゃないですか』
と言った小西に県の永井係長が言った。
『おめえ、学術協力って、何だか知ってんのか』
『だからあちこちの大学とか病院が協力して』
『情報統制だよ、情報統制』
小西はぽかんとした。
『つまり個々の大学病院や研究施設で、てんでばらばらのことを言われちゃ国民は混乱する、と。そんなことで、情報を一カ所に集めて、窓口を一本化して提供するって、それだけのもんだ』〉
やがて小西は房代の指示を受け、大学病院に忍び込み、重要なマイクロフィルムを手に入れます。感染源を知る重要なフィルムでした。その病院ではまっとうな方法でワクチンの研究をしていたのですが、その過程で遺伝子のいたずらか、研究者に手違いで自然に存在しないウイルスを造りだしていたのです。それが、オカモノアラガイと蚊、さらに人へと感染していきます。
新型脳炎は市から県へ、さらに圏域を超え、都内へと広がりを見せるに至り、ようやく国が動き出します。
そんな時、インドネシアの製薬会社が厚生省に新型ウイルスに対応できるバイオワクチンの認可申請をしました。厚生省は「承認の手続きに1年半かかる」と、無視を決め込みますが、世論がそれを許しません。デモが起き、抗議が殺到。追い込まれた厚生省は承認に追い込まれます。やがて発生件数ゼロの日を迎えるーー。
〈人々の体に免疫ができたのだ。それも従来のワクチンの数倍の早さで。臨床試験は見事に成功したのである。そして9月の終わり、暑さはまだまだ厳しいというのに、市内の蚊やその他の小動物の体内から、突然、ウイルスは消えた〉
感染症が治まり、昭川市は死者101人を記録した。しかし、この物語の最後は、昭川市から50キロ離れた上野でオカモノアラガイが大量発生していることを印しています。『ペスト』と同様、感染症の再来を予期しています。
これらに書かれたように、人類の歴史は感染症との戦いの歴史でした。
ペスト、天然痘、インフルエンザ
ペストは、古くから記録が残り、最も古いのは東ローマ帝国で発生し、14世紀には黒死病と呼ばれヨーロッパで大流行しました。1億人が命を落としたといわれます。
16世紀にはスペインのコルテスがメキシコのアステカ帝国を征服していますが、当初は鉄の鎧やウマなどの武器で優位に立ちました。しかし、勝利を決定づけたのは武器ではありませんでした。
一人の奴隷が1520年にメキシコにもたらした天然痘の大流行で、アステカ帝国の半分が死亡しました。同じくスペインのピサロに侵略されたペルーのインカ帝国では、天然痘に免疫のない先住民の人口が20分の1に激減したといわれています(『銃・病原菌・鉄』ジャレド・ダイアモンド著草思社)。
北米にもアメリカ先住民が数多く定住していましたが、ヨーロッパ人がやってきた時にはすでにユーラシア大陸の病原菌によって、壊滅状態に陥っていたといわれています。
過去の歴史の教科書には、100万人のアメリカ先住民が住んでいた北米に、白人が住み着いたと書かれていましたが、最近の調査研究によると、当時のアメリカ大陸には2,000万人の先住民が暮らしていたことが示唆されているそうです(同)。
ハワイ諸島では、1779年にクック船長とともに梅毒、結核、インフルエンザが上陸し、1804年には腸チフスが流行し、50万人の人口が84,000人に激減しました。病原菌が歴史上の勢力地図を大きく塗り替えているのです。
19世紀から20世紀にかけてコレラが大流行し、1918~1919年にかけてはスペインかぜ(インフルエンザ)が世界を覆い、2,000万~5,000万人が亡くなったといわれます。
日本でもこの流行で38万人が死亡しました。
しかし、その後、病原体のワクチンの開発が進み、1980年に天然痘の制圧に成功しました。
ところが、2002年にはSARSが世界各地で発生し、世界で800人が亡くなり、さらに2020年に、今回の新型コロナウイルスが中国の武漢市ではやり、それは日本も含め、世界に広がっていきます。やがて特効薬が完成し、感染症はおさまることでしょう。
しかし、新たな病原体がまた現れ、人類を襲うことでしょう。感染症と闘いには終わりがないのです。