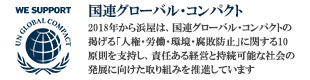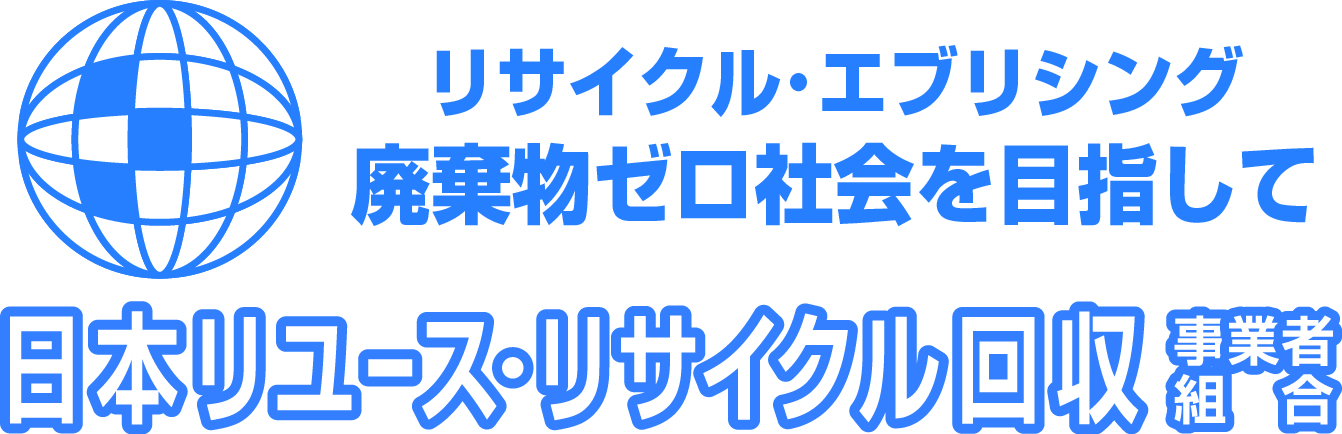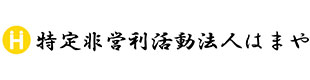そして、藤前干潟は守られた インサイドストーリー②

藤前干潟を守る会提供 転載禁止
名古屋市は、名古屋港に最後に残った藤前干潟を埋め立てごみの最終処分場にする計画を着々と進めていました。最後に環境アセスメントの手続きに入りました。その審査が通ると、運輸省(現国土交通省)が認め、埋め立て事業が着工できます。ところが、思わぬことが起きました。心ある数人のアセスの審査会の委員らが、干潟を守ろうと抵抗を開始したのです。
ジャーナリスト 杉本裕明
関連記事
環境アセスメントでの攻防
90年代半ば、市は埋め立て面積を46.5ヘクタールに縮小する前、市は、100ヘクタールに及ぶ西一区の埋め立て事業について、地元のコンサルタント会社、玉野総合コンサルタントに調査を委託していた。それが「西一区埋め立て事業に係わる環境影響評価調査報告書」としてまとまったが、市が内々に尋ねた専門家たちから「非科学的で恣意的(しいてき)」と猛批判され、公表できなくなり、お蔵入りさせたことがあった。
報告書は、例えば、「(干潟に生息するソリハシシギなど7種は)数が減少する可能性があるが、伊勢湾から姿を消すこと、特定の種が消滅することがない」。希少な水鳥が藤前から消滅しても伊勢湾のどこかにいれば良いとしていた。
水生生物は「調査区域810ヘクタールのうち埋め立てで消滅するのは13%」、陸生生物は、埋め立て地を植栽するので「陸上活動の場が増える。周辺の陸生動物相は豊かになる」。「(埋め立てで)シロチドリ、ハマシギなどは生息環境が好転し、増加する」と、利点を」強調していた。埋め立てた方が、環境がよくなるとは。
やがて46.5ヘクタールに計画を縮小した名古屋市は、市議会に「面積を縮小したことで、環境庁との調整もついた」と説明し、ことを進めようとしていた。しかし、環境庁の当時の幹部は「環境庁が縮小を求めたことは事実だが、それで納得したという記録はない」と否定する。これが伏線となって、のちに火花が散り、大爆発を起こすのだが、埋め立て計画を進めていた市の環境事業局には慢心があった。

杉本裕明氏撮影 転載禁止
1994年1月から環境アセスメントの手続きが始まった。事業が環境に悪影響を与えないように、事前に予測し、対策をたてる手続きのことを環境アセスメント(環境影響評価)と呼ぶ。当時は、環境影響評価法(アセス法)がなく、名古屋市の環境影響評価指導要綱に沿って行われた。
調査、準備書づくりは、東京に本社のある大手の新日本海洋気象(現・いであ)に委託された。その途中の95年7月、市は、新たに海底を掘削したり、嵩(かさ)上げを増やしたりして、年82万トンの埋め立てができる計画に変更した。これで全体の容量は、265万立方メートルから400万立方メートルに大幅に増えた。
アセスの手続きでは、その秋に準備書を縦覧する予定となっていた。本来は、アセスのやり直しが必要で、それを求める市民団体に、市は「大きな変更ではないので、必要なし」と突っぱねたのである。
ラムサール締約国会議で「干潟守れ」の手紙続々
96年3月、オーストラリアのブリスベーンでラムサール条約締約国会議が開かれた。オーストラリア政府から、同国から日本、アジア諸国を経由し、ロシアなどに渡るシギ・チドリ類を守る「シギ・チドリネットワーク」が提唱された。会議には、NGOとして、「藤前干潟を守る会」(名古屋港の干潟を守る連絡会から名称変更)代表の辻敦夫さんも参加し、藤前干潟の危機を訴えていた。日本国内の湿地で藤前干潟は、シギ・チドリの飛来数は2番目に多い。シギ・チドリ類にとって中継地を奪われかねない事態である。NGOや研究者らの声が届けられたブリスベーン市は、市長代行の名前で、西尾名古屋市長に手紙を書いた。

杉本裕明氏撮影 転載禁止

杉本裕明氏撮影 転載禁止
「(前略)オーストラリアの多くの鳥たち、特にブリスベーン市のモートン湾にねぐらを持つ種の中に、実際に藤前干潟に渡っているものがあると確信しました。私たち2つの都市は生態系のきずなでしっかりと結ばれています。(中略)問題の案件について善処されるよう市を代表してお願いします」
こうした手紙は、オーストラリアのダーウィン市長、ニュージーランドのオークランド市長、クライストチャーチ市長からも出された。これが、新聞やテレビで大きく報じられると、市は、市長の名前で、面積を縮小し、配慮したと釈明する手紙をこれらの市に送りつけたのである。
アセスの準備書が公開された
環境アセスメントの手続きが進み、96年7月に準備書が公開された。厚さは7センチもあり、重い。どの調査項目も結論として「影響は小さい」と結論づけていた。鳥類について「周辺地区全体に対する事業予定区域の利用率は、鳥類全体では1.3%、カモ類では1.0%、シギ・チドリ類では0.6%であった。シギ・チドリ類の採餌量は全干潟の最大で2%以下。以上により、埋め立て地による存在が鳥類に与える影響は小さいと考えられる」。
底生生物(鳥類の餌になる)について「事業区域内の底生生物はそのまま消失することが考えられる。しかし、周辺には225ヘクタールの干潟が残り、浅海域にも相当量の底生生物が生息していると推定されることから、影響は小さいと考えられる」。どの項目もこんな調子だった。

杉本裕明氏撮影 転載禁止
だが、準備書は、周辺地区の面積を過剰に広げ、さらに藤前干潟の鳥が餌をついばみにくる干出の時間帯を避けて調査をし、影響を小さく見せかけているのだった。やり口は、市が前に非公開にしていた報告書と同じだった。同社に務めたことのある元社員は、筆者にこう語った。
「本当のことを書いて、委託を受けた自治体に持っていった。環境への影響があるという結論だった。役所の担当者は『こんなもの受け取れるか』と言って、突き返された。そこで内容を変え、影響は小さいという結論をつけた準備書をつくり、提出した。発注者の名古屋市が気に入るような準備書をつくったのではないか」
アセスは、環境保全措置を取って環境への悪影響を未然防止するためのものだが、こうなると、何のための仕組みなのかとなってくる。
大もめになった第2分科会
一握りにすぎないが、それを憂慮した人たちがいた。名古屋市の指導要綱では、準備書が出ると、市長が審査書を作成し、事業者に送ることになっているが、その作成に当たっては、環境影響評価審査会の意見を聞くことが定められている。
審査会は、大気・水質などの公害関連の第1分科会と、自然関連の第2分科会に分かれ、大学教授ら専門家が審査した。第1分科会がすんなり進んだのに対し、第2分科会は大もめとなった。小笠原昭夫さんは学校の教師を退職後、愛知女子短期大学の非常勤講師で、鳥の専門家だった。野鳥の会の活動も長い。正義感が強く、藤前干潟のかけがえのなさを知っていた。第1回の会議の冒頭、小笠原さんが言った。
「鳥の干潟利用率が小さく出ているが、正しい数字を反映していません。干潟が干出している時間は短いが、その時には集中的に利用しています」
そして、おかしな調査なので、調査した人に会わせてくださいと、市の事務局に頼んだ。事務局の担当者は「前例がないので」と渋り続けた。調査をした側が出てこないので、小笠原さんがいくら質問しても、事務局から返答がなく、これでは審査ができない。
4回目の分科会で、「出てこないなら、私は次の会議に出ません」と通告した。次の5回目にやっと新日本海洋気象の社員が出席した。小笠原さんが尋ねた。
「トウネンはたった33グラムの鳥です。それなのに、どんなものを食べたか特定していますが、どうやって調べたのですか」
社員が「双眼鏡で見たり、そばに来たところを観察したりして出しました」
小笠原さんが言った。
「あなた、こんなデーダ出して恥ずかしくありませんか」
「その恥ずかしい–そう言われましても–」と、社員が口ごもった。
準備書は、トウネンとダイゼンの採餌調査を見ると、トウネンは重さ33グラムでスズメと同じぐらいの大きさ。それなのに、7倍も大きいダイゼンより食べる量が多いとしていた。他の委員が追った。「こんなことがわかるわけがないんだ」。市は、「こういうデータの出し方をやめます」というと、準備書に書かれた数字が次々と、「不明」と訂正されていった。
第1分科会は、早々と容認
2つの分科会のうち、第1分科会は、もめることもなく、事務局ペースで進められていた。第2分科会の委員の教授は、ある日、第1分科会で、道路・交通が専門の教授とタクシーに同乗したことがあった。教授が言った。
「第2分科会は、何をもたもたしているのですか。道路・交通の調査は、やっても1回です。鳥は毎月、1年やった。何が足りないのですか」
第1分科会の座長は、「処分場ができなかったら、市のごみがまちにあふれてしまいます」と、市の説明を信じ込んでいた。両分科会の審査の途中で、市の環境事業局の幹部が出席し、「ごみと私たち」というパンフレットを見せて市の窮状を訴えた。
「こんなに努力しています。これ以上は努力の限界を超えています」
名古屋市の家庭や商店から出る一般廃棄物は、1993年度に90.8万トン、95年度に93.4万トン、96年度に95.5万トンと増え続け、1998年には100万トンに迫る勢いだった。
ごみを燃やす清掃工場は、新南陽工場、猪子石工場、富田工場などが整備され、1981年に岐阜県多治見市に管理型最終処分場を確保していたが、増え続けるごみに合わせて施設を増強するというのが市の方針だった。1994年に「ごみ減量化・再資源化行動計画」を策定するが、市民と事業者にごみの発生抑制や減量、リサイクルを促すだけであった。 埋め立て量を減らすために、不燃ごみを破砕する大江破砕工場の建設が1993年に着工、97年3月に竣工した。西尾武喜市長からバトンタッチした松原武久市長は、そのパンフレットの挨拶文にこう書いていた。

杉本裕明氏撮影 転載禁止
「大量消費社会を改め、資源循環型社会の構築を図ることが緊急の課題となっております。この工場は、従来埋め立てていたごみの中から、鉄及びアルミを抜き取り、資源として再利用していくことが可能となる施設であります。完成を機に、ごみ減量・再資源化を一層推進して参りたい」
しかし、筆者が破砕工場を尋ねると、工場幹部が嘆いた。「粗大ごみと不燃のごみを中心に搬入されるはずなのですが、半分近くが紙ごみなんです。それを分別し、焼却工場に送っています」。軟性のプラスチックが絡まり、破砕機は何回となく、停止を余儀なくしていた。
収集されるごみは、一般ごみと分別ごみのわずか2分別。紙ごみは古紙としてリサイクルされず、多くの紙ごみが一般ごみと分別ごみに混入していた。空き缶と空き瓶の回収は16区のうち6区でモデル的に行われているにすぎず、市は「2000年を目途に拡大したい」としていた。
しかし、この当時、容器包装リサイクル法が1997年に施行され、缶、瓶に加え、ペットボトルの収集が始まっていた。2000年からは、それ以外のプラスチック容器包装の収集・リサイクルに拡大し、社会はリサイクルに大きくカジを切っていた。循環型社会の扉、リサイクル新時代の夜明けというのに、名古屋市は、まだ闇の中にあった。ごみを減らすのではなく、ごみの増加に追いつこうと、施設造りに邁進していたのである。
分科会では、環境事業局の幹部が、名古屋港の地図を広げた。そして、「このへんですか」と、指さし、円を描いた。藤前干潟の南側に人口干潟を造ろうと考えているというのだ。委員らは、それを聞かされても、半信半疑だった。まさか、それを後に市が実行に移そうとするとは、誰も予想だにしていなかった。
議事録から消された小笠原委員の発言
その翌月、両分科会の調整会議が開かれ、市に答申された。結論としては、準備書の内容を「概ね妥当」とし、要望事項として、減量とリサイクルを進め、「廃棄物の埋め立て処分は、長期的展望に立って、次期の大規模処分場をこの地域外で確保することができるよう、早急に対応を進めるべきです」としていた。
両分科会を代表し、佐藤教授が「追加調査が行われ、調査結果を検討した結果、準備書に盛られた内容がほぼ妥当であると判断しました」と話した。小笠原さんが、手を挙げ反論した。
「座長が言ったことには、重大な間違いがあります。分科会は1年の追加調査を要望したのであって、秋だけ選んで行ってもらったのではありません。秋だけの内容を検討しておおむね妥当と判断したのであって、準備書の内容を正当づけたとは言っていません」
こうして1年にわたる審査会は終了した。この間、録音テープを回しながら、市は議事録を作成せず、最後のこの合同会議のみつくった。しかし、最後に小笠原さんが異議を唱えたくだりがなかった。あとでそれを知り、小笠原さんに問いただされた職員が言った。「勘弁してください」。自宅に帰り、テレビ局のスイッチを入れると、地元のテレビ局のインタビューで、環境事業局の幹部が誇らしげに答えていた。
「秋の調査をした結果、準備書の内容が妥当であるとわかりました」
アセスの事務局は環境保全局。役所の中では、事業を担う環境事業局の方が、力が強い。小笠原さんは、「勘弁してください」と言った保全局の職員の顔を思い浮かべた。
続きはコチラから
そして、藤前干潟は守られた インサイドストーリー③
藤前干潟を守る会の代表だった辻敦夫さんは、1996年5月、名古屋市が開いた第1回公聴会で、5番目に登
藤前干潟を守る会の代表だった辻敦夫さんは