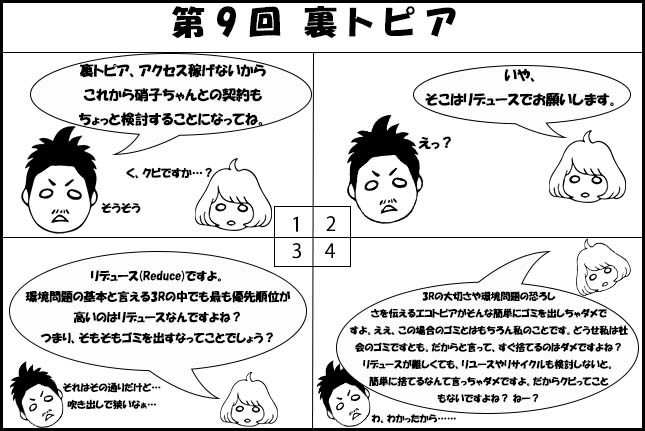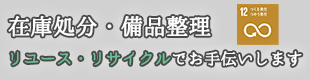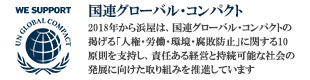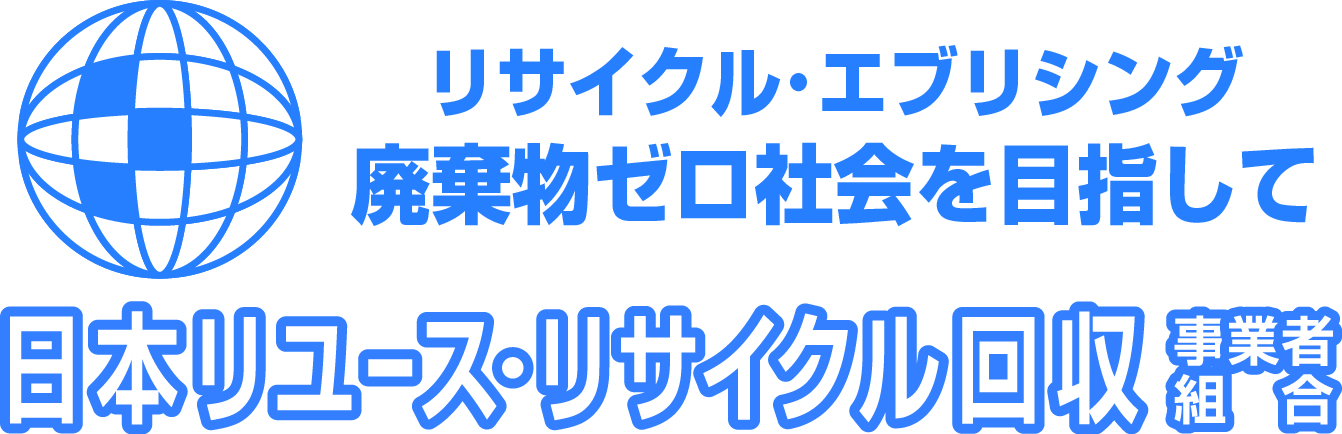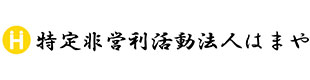アニメの舞台になった影響は?岐阜県飛騨市のまちづくりの取り組み ー オーガニックビレッジ宣言や珍しい広葉樹による林業の活用

東京圏の人口集中、少子高齢化によって地方経済は落ち込み、活性化の取り組みが必要とされますが、岐阜県の飛騨市では観光だけでなく、食や自然資源の活用に力を入れています。さらには人気のアニメ映画「君の名は」の舞台になったことで、ロケツーリズムに力を入れ始めたという経緯も。
今回は飛騨市のまちづくりの取り組みをご紹介します。アニメの裏話や広葉樹に焦点を当てた林業など、注目の取り組みが数多くあるため、ぜひ最後まで目を通してみてください。
人気アニメ映画の影響は?岐阜県飛騨市と「君の名は」
――飛騨市は映画「君の名は」の舞台として知られていますが、当時はどのような反応があったのでしょうか。観光客の増加などまちづくりの効果があれば教えてください。
映画公開前、「飛騨市が舞台になっているらしい」という不確かな情報を入手し、まずはそれが本当かどうか確認しようと、映画関係者の方々などと連絡をとり、試写会を観るところまでたどり着きました。見に行った職員から飛騨市の風景がとても美しく描かれ、内容も素晴らしかったと絶賛していたことから、それなら何かできないかと手探りで始めたというのがプロモーションのきっかけです。
例えば、主人公たちが飛騨古川駅を訪れるシーンで「ひだくろ」という実在する飛騨牛のPRキャラクターが映り込むのですが、これを再現するために所有する団体から着ぐるみを借りてきてパネルを設置したことが挙げられます。他にも、駅のホームを見下ろすシーンと同じ風景を撮影できるようフォトスポットをつくったり、市内に「飛騨市は君の名はを応援します」と書かれたポスターを貼ったり、少しでもお客様にきてもらえるような環境を作りました。

提供:飛騨市
また、SNSで「このシーンに出てくる場所のモデルはどこだ?」と探される方も多いので、現地を訪れたら自然とその景色を見つけられるよう仕組みも準備しました。事前にすべての情報を公開してしまうと、ネットで見て満足してしまう人も多いだろうと考え、モデルとなった場所の近くに映画のポスターを貼るなど、少しずつヒントを出すような形を取りましたが、今思うとそれが効果的だったかもしれません。試写会の時点から少しずつ多くのお客様が訪れるようになりました。
それから、ラッピングバスや散策マップ、ノベルティなどロケツーリズムの取り組みを公開から始めます。映画に出てくるバス停も再現度を高めるために、そのシーンに出てくるポスターと同じものを貼って、フォトスポットを作りましたが、そこに置かれた記念ノートには現在も書き込みがあり、国内だけでなく外国の方も来られているようです。

提供:飛騨市
映画の効果でどれだけのお客様が訪れたのか、正確には分かりませんが、作中に登場した飛騨市図書館も記念ノートが置かれていて、その書き込みと入館者から推計したところ、公開から約3年半で17万9千人の方が訪れたのではないかと思われます。2023年に新海誠監督の「すずめの戸締まり」が公開されたときも、それを見て「君の名は」の聖地巡礼しようというお客様が増えたので、明らかに映画の影響は大きかったと言えるはずです。
当時はロケツーリズムを積極的に取り組んでいませんでしたが、これ以降は支援に力を入れています。こういったロケ選びは監督の意思よりも、制作会社が調整しやすい場所が選ばれる傾向があるようです。だから、体制が整っていない地域に「ロケをしたいです」と言ってもハードルが高いため、飛騨市がスムーズに受け入れられるよう、市民や観光事業者に対してセミナーの開催や、制作者をお招きしてロケハンのツアーを行っています。その効果もあってか、ドラマや映画の受け入れなど実績が増え、現在も2本ほど進行中です。
他にも、思わぬ効果として「君の名は」のファンで県外からやってきて入職した職員もいれば、聖地巡礼者と地元の人の間で交流が増えたことも挙げられます。地元の人からすると何もないところに観光客がやってきて喜んでくれるため、市民の郷土愛につながっているようです。そのためにも、今後もこういったロケツーリズムに力を入れたいと考えています。
関連記事
「君の名は。」の聖地巡礼!モデルは諏訪湖?ロケ地を巡る
日本が世界に誇るコンテンツ、アニメーションは心打つストーリーや背景の描写力が評価され、多くの人から愛
日本が世界に誇るコンテンツ、アニメーショ
飛騨市によるオーガニックビレッジ宣言
――地域経済の活性化として、飛騨市ではオーガニックビレッジ宣言を行っているとうかがっています。そもそもオーガニックビレッジ宣言とは、どのような取り組みなのでしょうか。具体的な取り組みも含めて教えてください。
オーガニックビレッジ宣言は、農林水産省が2021年に策定した「みどりの食料システム戦略」が大きく関係しています。こちらは、持続可能な食料システムの構築と環境負荷の低減を目指した戦略で、日本の有機農業に関する栽培面積を増やすことが目標です。そして、オーガニックビレッジ宣言として手を挙げた自治体に対し、3年間100%補助の交付金を充てて、有機農業を全国的に広めています。飛騨市は2025年3月にオーガニックビレッジ宣言を行いましたが、これは岐阜県内では2番目となります。
具体的には「飛騨市種を蒔くプロジェクト」として、大きく分けて4つの取り組みを行っています。1つは人材育成。有機農業の課題として一般的な農業に比べると技術が確率されていない、という点です。さらに、2つ目として栽培管理の技術面が挙げられ、これらは栽培向上に向けた有識者を呼ぶ、ロボットを導入するなどによって改善を目指しています。

提供:飛騨市
3つ目は販路や流通販売の課題です。慣行農業はJAさんが大型のスキームとして栽培したものを買取り、ある程度は市場に流してもらえますが、有機農業は量も少なく、販路も自分たちで確保しなければならない、という課題があります。これらを市がサポートするため、レストラン・旅館などと生産者のマッチングを行う、首都圏から有名なシェフの方にお越しいただき、農家さんの圃場で見学していただくなど、販路の開拓を行っています。
4つ目は有機農業に関する理解の醸成です。飛騨地域は慣行農業がメインですが、地域の皆さんに有機農業の理解をしていただくために、講演会や料理教室、市民参加型イベントの開催、他にも学校給食に有機農業で栽培された野菜を使用するなど、さまざまな取り組みを行っています。
――農業に関係する取り組みと言えば、飛騨市の食に焦点を当てたWebサイト「HIDAICHI(ヒダイチ)」も運営されているようですが、こちらはどのような目的で立ち上げたのでしょうか。
HIDAICHIは飛騨市で作られる自慢の食材を紹介するために立ち上げました。と言うのも、HIDAICHIができるまで農家の方々は、農作業が忙しくて現場を離れられないため、営業活動が難しい状況でした。そのため、市の職員が商談会に出たり、シェフの方と話したり、代わりに営業活動を行おうとしたのですが、飛騨市にどんな食材があるのか詳しく説明できず、どうにか情報を1つにまとめられないか、という課題を目の当たりにします。そこで、HIDAICHIを立ち上げることになりました。

提供:飛騨市
最初はパンフレットみたいな形で作成することも考えられましたが、誰にでも見てもらえるためにも、Webサイトとして立ち上げました。さまざまな自治体が観光サイトをお持ちだと思いますが、食の総合サイトとして農家さんに焦点を当てたものは珍しいと思います。具体的な内容としては、飛騨市の広葉樹が良質な堆肥となった地表から湧き出た水によって作られる農作物の豊かさ、農家さんによる日々の取り組み、やりがいなどの発信です。食材を季節で探すことができたり、飛騨市の食材を使ったレシピを招待したり、森、水、土、食の親和性を背景にし、生産者さんのこだわりや農家さんによる自慢の食材を紹介しています。
特に注目は飛騨市と言えば飛騨牛です。他にもお米、最近だとアユも注目されていて、宮川と高原川の清流で育った天然ものは首都圏の老舗和食料理店でも取り扱っていただいています。
参考:飛騨市公式 食の情報サイト HIDAICHI(ヒダイチ)
林業に適さないはずの広葉樹で地域経済を活性化
――飛騨市は広葉樹を活かしたまちづくりに力を入れているとうかがっています。こちらは、どのような取り組みなのでしょうか。
飛騨市は93%が森林で、そのうち68%が広葉樹天然林という地域です。これを地方創世の観点で活用できないか、ということで取り組みをスタートしています。まず広葉樹が何に使われているのか調査したところ、国内で伐採されているうち、ほぼ9割がチップ(木材を粉砕して作られた小片で主に製紙の敷材の原料として使われる)となり、家具などの製材としての利用は4.4%程度でした。
実際、飛騨地域は家具制作で有名な産地でもありますが、ほとんどの木材は輸入された木材が使われています。これは全国にある家具の産地も同じ状況で、特に国産の広葉樹はほとんど使われていません。と言うのも、針葉樹であれば人工的に植生されているため、真っ直ぐ太く、植えてから30年ほどで育ち、樹種も画一です。そのため、生産効率よく安定した林業が成り立ちます。

提供:飛騨市
しかし、広葉樹は細いものも多く、樹種もミズナラ、朴の木、ブナなどさまざまで曲がりや節も少なくありません。さらに、飛騨市は平均70年生の広葉樹が多く、これは戦後に炭や薪として使うために伐採され、そのあと育った二次林ですが、胸高直径(胸の高さの直径)の平均が約26センチというサイズがほとんどで、これは家具として使うには細くて使いにくい大きさです。だとしたら、すべてチップにしてしまった方が効率はいいと考えられていましたが、それは安価に取引されるだけで大きな収益にならないことを意味しています。
その反面、飛騨市には森林組合や広葉樹を製材としている専門の製材所だけでなく、家具メーカー、木工作家さんもいらっしゃいます。これだけ揃っていれば、サイズの小さい広葉樹も地域の重要な資源として、新たな価値を加えられるのではないか、と10年前からさまざまな取り組みが進められました。
また、タモやナラといった木がワシントン条約に登録され、昨今の円安の関係で良質な海外産の原木が確保しにくくなっている背景もあり、広葉樹の需要が当時と比べて増えている、という状況です。だとしたら、今後は国産広葉樹の活用が避けては通れないだろう、という考えもありました。
課題を整理すると、市内で伐採された広葉樹の約94%がチップとして安価で販売され、残りの約6%が建築や家具の製材として市内で使われていることになる。チップとして売れることは決して悪いことではありませんが、それは市外の工場で使われるため、市内で経済を回すという視点で見ると、何かしらのテコ入れが必要です。
そこで始めた具体的な取り組みの1つが、事業を牽引する主体として会社を作ることです。行政が出資した第三セクターと言われる会社ですが、森林・林業のトータルマネジメントを行う株式会社トビムシさん、空間デザインなどを得意とする株式会社ロフトワークさんと協力して「株式会社飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)」を設立しました。
トビムシさんは都市部へのチャネルを活用した新たな商品の販売や林業・木材流通の新たな仕組みづくりを、ロフトワークさんは国内外のクリエイターネットワークを活用したものづくり人材や異業種との交流を生み出すことを得意としています。それに飛騨市の広葉樹と高い木工技術を加え、価値の高い木製品の企画・制作・販売を可能とするための会社がヒダクマです。
事業の例としては「FabCafeHida」の経営が挙げられます。こちらはコワーキングスペースとして使えるカフェで、木製品の企画・開発・プロトタイピングだけでなく、イベントの開催や滞在(宿泊)も可能。国内外のクリエイターが訪れ、広葉樹の新しい可能性を創造する場となっています。その他にも、小径木広葉樹を使ったキャットツリー、オフィスリノベーションなど。さらには広葉樹を中心に自社のオフィスを作って、建築材としても活用できることもPRしました。

提供:飛騨市
もう1つの具体的な取り組みは、流通の仕組みを作ることです。それまでは、伐採された広葉樹は山土場に集められ、伐採業者の目線で「これはチップ」「これは製材用」と仕分けが行われていました。しかし、木工作家などの作り手の方から見ると、チップとして仕分けられる広葉樹の中にも、十分使えるものがあったため、伐採業者の仕分けだけで流通してしまう仕組みを変える必要があったのです。
そんな状況を改善するために「飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアム」を設立しました。これは素材生産者や製材事業者、建築事業者など広葉樹が伐採から商品になるまでに関係する人々を集めた任意団体で、会員がそれぞれの役割を明確にし、地域内のサプライチェーン構築を目指すため、2020年に設立しています。
コンソーシアムを設立したことで、多くの関係者から意見を集め、実際は広葉樹に多様なニーズがあることが分かりました。さらに、以前は多様な広葉樹を活用できる方のマッチングが難しかったところを「広葉樹活用コンシェルジュ」の配置によって改善。多様な使い手・作り手とマッチングできるようになりました。
また、原木の見える化のために流通拠点として市内に中間土場を設けて、そこで木が持つ特徴を見極め、どこに売れるのか、より詳細な仕分けを行えるようにしました。木工作家さんも直接訪れることもできるため、こちらでコンシェルジュと相談し、使いたい木が手に入る、という仕組みです。これによって、チップになっていた広葉樹も別の活用法が発見され、新たな原木・製材販売ルートが生み出されました。山の斜面によりますが、6%しか製材用として使われていなかったところが、20~30%程度に変わり、チップより高い価値で販売されるようになっています。

提供:飛騨市
ちなみに、飛騨市の広葉樹が質的に優れているのかと言えば、他の地域のものと大きくは変わりません。そんな中、価値を付けるための努力も行っていて、伐採された木は通常、家具などに使うためには一年半ほど乾燥させる必要がありますが、それを三ヵ月程度に短縮する技術を試験的に運用しています。
あとは、地域社会や自然にとって適切な森林管理が行われていることを認証するFSC認証制度の「FM認証」を飛騨市が取得し、その認証を受けた森林から産出された認証木材が適正に流通・使用していることを証明する「CoC認証」をヒダクマが取得しました。こういった価値付けに加え、飛騨市で伐採された広葉樹がどれだけ温室効果ガスを排出しているのか、三重大学と協力して調査しているところです。全国的に広葉樹の関係で温室効果ガスの数字を出しているところはほとんどないので、これは珍しい取り組みだと思います。
飛騨市が目指す自然と共存したまちづくり
――FM認証を取得されているとのことですが、広葉樹の持続可能性はどのように心掛けているのでしょうか。
林業は針葉樹がメインなので、広葉樹の伐採はどのように制御すべきなのか、たくさんの試行錯誤を重ねる必要があります。例えば、針葉樹は間伐によって樹木を太く成長させられますが、広葉樹も同じことができないかと試しました。しかし、間伐はできても広葉樹は枝が横に張っているので余計に切ってしまい、使えるものを捨てることになってしまうケースがほとんどで、これではコスト的にも無駄が多いと、模索を重ねた結果、帯状に伐採する方法が最適でないか、という結論に至っています。

提供:飛騨市
これは、1回の伐採面積は3ヘクタール未満、伐採幅はおおむね樹高の2倍程度にするなど、独自の基本方針を設けて切り、次に育つものを効率よく残すという方法です。伐採した後の状況も調査を行い、更新を考えた収穫を行う持続可能な林業を目指す。つまり、収穫、活用、更新、育成を通じて林業が成り立つように取り組んでいます。
これらの取り組みによって、飛騨市の森から伐採された広葉樹が、仕分け、製材から加工制作、エンドユーザーまで顔が見える仕組みとなりました。原木の一本一本に仕分けのマークを付けて、どこの斜面で伐採されたのか、細かく仕分けしているため、極端なことを言うとエンドユーザーに、どこの木によって作られた商品なのかピンポイントでお伝えすることも可能です。
また、全国的に広葉樹の製材所が減っている中、飛騨市は過去に使われていた製材所を再稼働させました。これは広葉樹を活用したまちづくりにおける、成果の1つと言えるでしょう。他にも、広葉樹活用による企画・提案力が養われ、さまざまな事業者さんの期待にお応えする機会も増えています。これからも、資源利用に必要な仕組みを持続的に試行していきたいと思います。
――広葉樹やオーガニックビレッジ宣言など自然と共存したまちづくりの重要性を教えてください。
例えば広葉樹のまちづくりだと、メーカーさんが「ナラが欲しい」と言ったら、指定された量のナラを切らなければなりません。つまり、人間の要望に合わせて自然を歪めるわけです。
だから、森林で言えばその地域にある森林に合わせた産業を意識するべきだと思います。自然を歪めるのではなく、そこにある自然に合った施業や商品を考えるなど、人間の方が合わせる。広葉樹もオーガニックビレッジも、自然に沿った取り組みを意識しています。
そこにある自然を活かした産業こそ、持続可能なまちづくりを実現するのではないでしょうか。