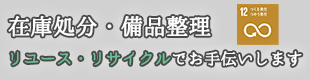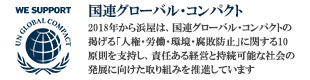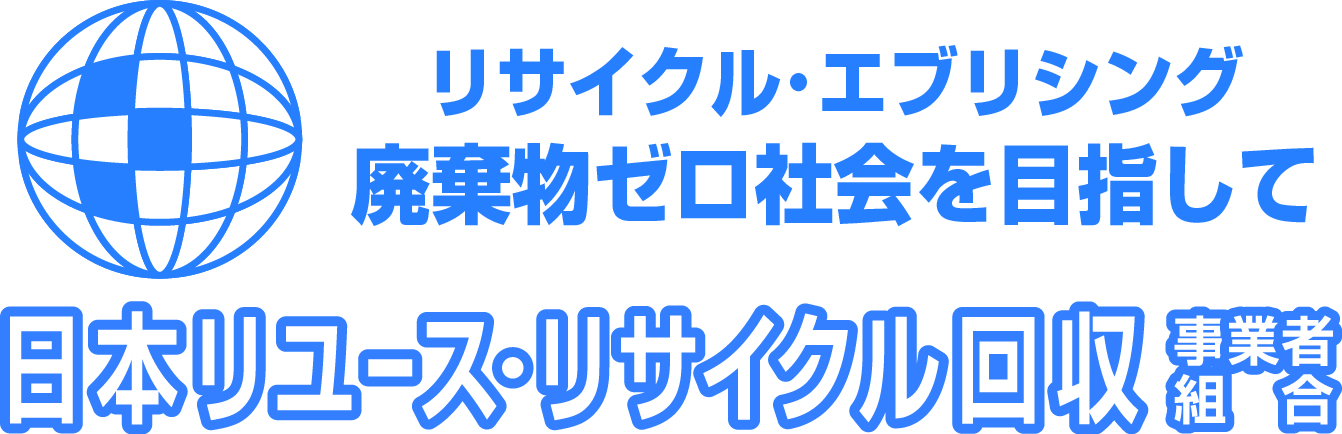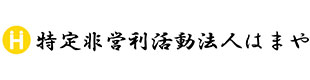グリーンウォッシュとは?エコを謳う商品や企業の特徴

ここ最近は、サスティナブルやエシカルといった言葉を頻繁に聞くようになりました。 しかし、同時にグリーンウォッシュという言葉も頻繁に聞くようになっています。
グリーンウォッシュとは、どういう意味なのでしょうか。 グリーンウォッシュの定義や特徴をご紹介します。
目次
グリーンウォッシュとは?上辺だけの環境保護が話題
グリーンウォッシュとは、環境に配慮しているイメージの「グリーン」と、上辺という意味の「ホワイトウォッシュ」を組み合わせた造語です。 つまり、上辺だけで環境保護に熱心だと見せかけることをグリーンウォッシュと言います。
グリーンウォッシュは1980年代半ばから欧米の環境活動家を中心に使われ始めました。 環境意識が高い消費者に選ばせるよう、環境に優しい、地球に優しいといった表記がある商品でも、実際はそのような効果がないものをグリーンウォッシュ商品と言います。
具体的な例としては、いくつかあります。 実際は危険物質が含まれているにも関わらず「省エネ」といった表示を記載するなど、意図的に情報を隠蔽する。 以前から使用が禁じられている物質を、あえて未使用だと謳う。証拠がない曖昧な表記。より悪いものと比較するなど。 グリーンウォッシュは、80年代後半から90年代にかけて、広告キャンペーンに森林や海洋の写真を使うことで、グリーンな印象を持たせていましたが、現在はさらに洗練され、実績をアピールする形に移行しています。CSR報告書などもグリーンウォッシュのツールに用いられていることもあるのです。
グリーンウォッシュは恐ろしい?環境負荷を増やす危険も
このようなグリーンウォッシュが蔓延してしまうと、恐ろしい結果を生むことになります。 グリーンウォッシュの恐ろしい点とは、どういった部分なのでしょうか。その例を見てみましょう。
グリーンウォッシュ企業が増加する恐れ
多くの人は商品に「天然由来の成分配合」と書かれていたら、何となく環境にいいかもしれない、と購入してしまうかもしれません。 それを気付かずに続けてしまうと、グリーンウォッシュ企業は利益を上げて成長してしまいます。 そして、そのような企業が増えてしまったら、本当に環境に良い取り組みが激減してしまうこともあり得るでしょう。
環境に悪影響を与える恐れ
グリーンウォッシュは環境に良いとアピールしていますが、それが事実ではありません。 それでも、環境に良いと信じて商品を購入しても本当は環境に負荷を与えてしまうことになります。
さらに、このようなグリーンウォッシュが増えてしまうと、消費者も「環境に良い」と謳う商品やサービスを信じられなくなってしまいます。 それにより、本当に環境に良いエコ商品も売れなくなってしまい、環境負荷が増してしまうことも考えられます。
企業はイメージダウンしてしまう恐れ
昨今では企業のあやまちは、SNSなどインターネットで広く拡散されてしまうことがあります。 そうなるとグリーンウォッシュを行っていた企業は、イメージを損ねてしまい、利益も失ってしまうでしょう。 グリーンウォッシュは最終的に、誰も得しない状況を作ってしまうと言えるのです。
グリーンウォッシュを見抜くには?10の特徴に注意
このようなグリーンウォッシュを見抜くために、消費者の私たちはどのような点に注目すべきでしょうか。 イギリスを拠点とし、持続可能なコミュニケーションを推進するFuterra社が中心となって発行された「Understanding and Preventing Greenwash: A Business Guide」には「グリーンウォッシュの10のサイン」が掲載されています。
- 曖昧なキャッチフレーズの使用
(例:エコフレンドリー、環境に優しい) - 裏の顔がある企業の商品
(例:汚染物質を川に流す工場で作られる高効率電球) - 暗示させるイメージや写真を使っている
(例:煙突から花が咲くなど環境に優しいイメージ) - 適切ではない主張
(例:主な事業による環境負荷を報告せず、小規模な環境活動を大々的に主張) - 「〇〇でナンバー1」という主張
(例:同業者や同等モデルなど環境に優しくないものと比較することで、少しでもエコであることを主張) - 信頼できないグリーン商品
(例:エコフレンドリーなタバコ、といった危険であるにも関わらずエコだから安全だと誤解させる) - 理解できない言葉を羅列
(例:広告に科学者や専門家にしか理解でいない表現を並べる) - 作り出した第三者機関による評価や認証
(例:第三者機関の認証に見せかけ、実は自社で作った認証ラベルを表示している) - 証拠が不十分な主張
- 捏造や偽造
参考:BSR Understanding and Preventing Greenwash: A Business Guide
エコを謳う商品を購入するとき、企業のCSR報告書を見るとき、これら「10のサイン」に該当するものがないか、ぜひ意識してみてください。
グリーンウォッシュの具体例とは?
グリーンウォッシュの意味や危険性は先述した通りですが、具体的にはどのような事例があるのでしょうか。 企業の取り組みや環境にいいと言われるエコアイテムに関するグリーンウォッシュをご紹介します。
企業によるグリーンウォッシュ
企業は環境問題を改善するさまざまな取り組みを行っていますが、すべてが上手く行っているかと言えば、そうではありません。 例えば、マクドナルドは2018年に一部の店舗でプラスチック製のストローから「100%リサイクル可能」と謳った紙製ストローに切り替えました。 しかし、ストローの強度を高めたことでリサイクルが困難となり、結局は廃棄してしまい、多くの批判を受けました。
H&Mは2019年に「コンシャスコレクション」というキャッチフレーズで、リサイクル素材を使用した商品を売り出します。 しかし、リサイクル素材の使用量など十分な根拠が示されていなかったため、ノルウェー消費者庁から「違法なマーケティングの疑いがある」と非難を受けてしまいました。
エコアイテムのグリーンウォッシュ
私たちの身の回りで、エコアイテムとして紹介されるものは数多く存在します。 マクドナルドの件で触れた紙ストローもその1つです。 プラスチックを使用しない紙ストローは環境にいいと言われます。 しかし、紙ストローは二酸化炭素を吸収する木を伐採してつくられていることは忘れられがちです。 また、紙を生産するには、プラスチックよりも多くのエネルギーを消費するという話もあり、絶対的に環境にいいものとも言い切れません。
他にも、エコバッグは製造から輸送までのコストを考えると、二酸化炭素の排出量はレジ袋の50~150倍になるという指摘があります。 私たちがエコバッグをエコに使うためには、50~150回ほど使用する必要が出てくるのです。
グリーンウォッシュが増えないために意識すべきこと
環境を破壊してしまう恐れがあるグリーンウォッシュが広まらないために、私たちにできることはあるのでしょうか。 エコを謳う商品は、世の中に多く存在するため、私たちはグリーンウォッシュを見極める目を養わなければなりません。
手間はかかってしまいますが、商品を手にするときは、どこでどのように作られているのか考えることが重要です。 それを心がける消費者が増えれば、企業側もグリーンウォッシュはデメリットしかない、と認識する日がくるでしょう。 また、SDGsの取り組み、サスティナブルな活動を知るだけでも、そのような知識が身に付きます。 ぜひ試してみてください。