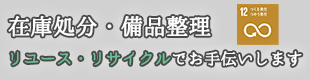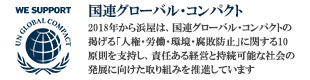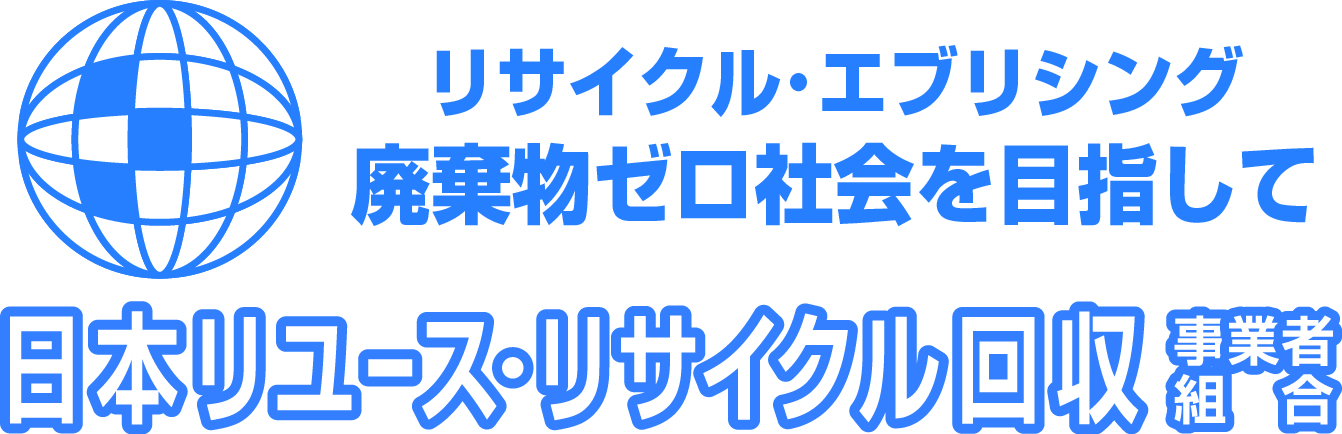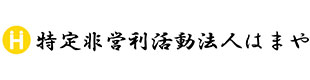外来種による深刻な問題!どんな悪影響があるのか?

いま日本に存在している様々な野生動物が危機に晒されています。 その危機をもたらすのは、外来種と言われる動物です。この外来種は環境問題の一つとして、広く話題になっています。
それでは外来種とは、どのような動物なのでしょうか。 また、外来種による問題とは、どのようなものなのでしょうか。そして、なぜ外来種は日本にやってくるのでしょうか。
関連記事
ヌートリアとは?食性や危険性など外来種の特徴を解説
【意外と恐ろしい】ネズミが発生!危険性や対処法をご紹介
動物由来感染症のまとめ10選!動物から人に移る病気とは
外来種とは?問題視される理由
外来種とは、もとはその地域にいなかったにも関わらず、様々な理由で他の地域から入ってきてしまった生物のことです。 外来種は、もとからその地域に存在していた在来種の生息地を奪うことがあり、それによって生態系のバランスが崩れてしまうことがあります。
ほとんどの外来種は、訪れた場所で定着することはありません。 気候など環境が合わず、短い期間で消滅してしまうのです。 しかし、原産地では問題なく生息していた生物が、侵入した先で侵略性を発揮してしまう場合があります。 外来種が訪れた新たな地域では、天敵が存在しないことがあり、それによって成長と繁殖が向上するのです。
外来種は国外からだけではなく、国内の他の場所から移動してきたものも含みます。 例えば、同じ日本国内であっても、海に囲まれた島であれば独自の生態系が作られていることがあり、そこに国内の別の地域の動物が持ち込まれてしまうことで、バランスが崩れてしまうこともあるのです。
外来種問題の原因は主に2つ
外来種の定義の一つとして「人間によって別の地域から導入された生物」ということが挙げられます。 明治時代以降は、急激に国土開発が進んだことから、野生生物の住む場所が減ってしまいました。 また、飛行機や船で外国から持ち込まれた生物が、その地域で定着してしまうことも増えてしまったのです。
人間によって持ち込まれるパターンにも2通りが考えられます。 それは意図的な導入であるか、そうでないのか、の2通りです。
意図的なケース
意図的な場合として考えられる例は、ペットや家畜として導入されるケースがあります。 特定の場所で飼育されていたとしても、管理不足により動物が逃げ出してしまったことで野生生物として繁殖してしまうのです。
非意図的なケース
非意図的である場合は、人間が移動の際に、どこかに付着、寄生してしまったことで、別の地域から導入されてしまうケースです。 植物の種子や昆虫などに多くあるケースだと言えるでしょう。
外来種による問題の影響
具体的に、外来種はどのような影響をもたらすのでしょうか。
生態系への影響
生態系は長い時間をかけて形成されるもので、生き物たちの食物連鎖や住み分け、関わり合いなどが、自然なバランスで成り立っています。 そこに外来種が入り込んでしまうと、もともとその場所にいた在来種が追いやられ、自然のバランスが崩れてしまいます。 他にも、外来種が近縁の在来種と交雑して雑種を作ってしまうことで遺伝子汚染が起こってしまいます。
農林水産業への影響
外来種が田畑を荒らしてしまうことや、漁業の対象となる生物を捕食してしまうことで、危害を加えてしまうケースがあります。 近年、都内でアライグマによる相談が増え、農作物だけでなく住居が荒らされることもあるようです。
人の生命・身体への被害
外来種の中には毒を持っていることがあります。そんな生物に噛まれたり刺されたりしてしまうと大変危険です。 本来であれば、その地域にはなかった病気の発症や感染の危険も考えられるのです。

恐ろしい!日本の生態系を脅かしている危険な外来生物10選
生態系のバランスが崩れてしまう原因の一つとして、外来種による脅威が挙げられます。 外来種の中に
生態系のバランスが崩れてしまう原因の一つ
外来種問題の対策
このような外来種の問題を解決するために、2005年に外来生物法が施行されました。
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」と言って、外来生物による危害を防止するために制定されました。
明治時代以降に持ち込まれた外来種のうち、特に問題視されているものを「特定外来生物」に指定することで、その生物の飼育や栽培、運搬から販売などの行為を禁止しています。
既に定着してしまった特定外来生物については、必要に応じて駆除を行うよう指導しています。
外来種の問題は人間の活動によって、繁殖してしまった生物の問題であり、単純に駆除することで解決するには、微妙な問題と言えるかもしれません。 そのため、人間は責任を持って自分たちが管理できるものは管理を徹底し、自然のバランスを崩さないよう、注意する必要があるでしょう。

生物多様性をビッグデータ化!環境保全の新たな形 久保田康裕教授インタビュー
私たちの生活にさまざまな恩恵をもたらす生物多様性ですが、人間の活動によって失われる恐れがあります。
私たちの生活にさまざまな恩恵をもたらす生