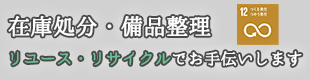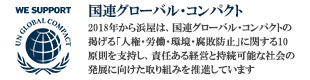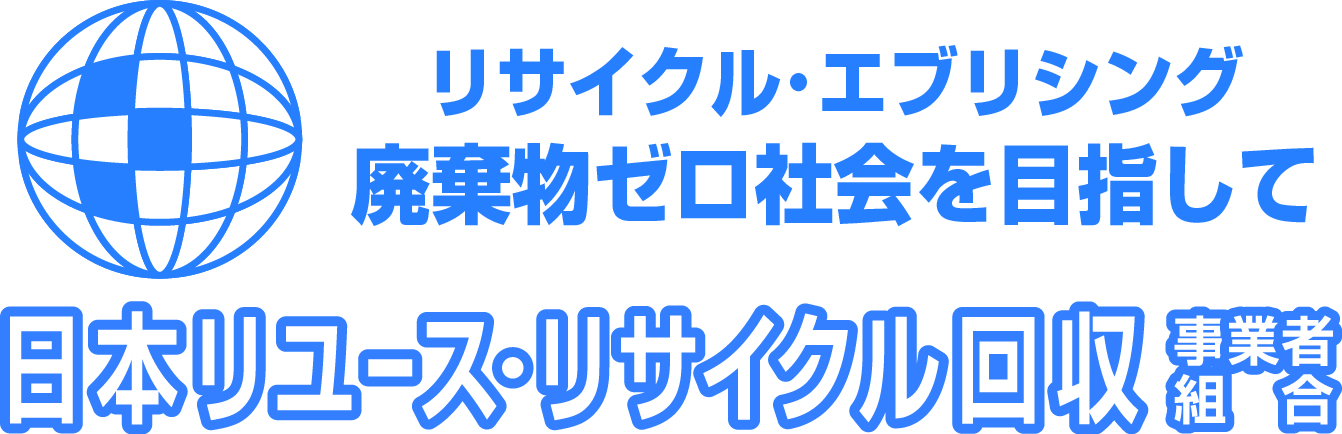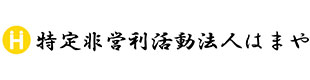【宇宙のごみ】スペースデブリとは?発生原因や影響を解説

宇宙と言えば何もない空間をイメージする人も多いのかもしれませんが、実はごみで溢れています。 宇宙のごみを「スペースデブリ」と言いますが、具体的にはどういったものが捨てられているのでしょうか。
今回はスペースデブリの意味や原因、危険性から対策までご紹介します。
目次
スペースデブリとは?宇宙ごみの発生原因は
まずはスペースデブリの意味、発生する原因、地上に影響があるのか、という点を確認してみましょう。
スペースデブリとは
スペースデブリ(space debris)とは、地球の衛星軌道上にある人工的な物体のうち、何らかの活動を行うことのないものを指します。 つまりは、宇宙に浮かぶごみを意味し、日本ではそのまま「宇宙ごみ」と表現されることも。 具体的には、運用を終えた人工衛星、ロケット打ち上げに使われた部品、爆発や衝突によって発生した破片などが挙げられます。
その数は、アメリカの連合宇宙運用センター(CSpOC:Combined Space Operations Center)が公開している数だけでも、2万を超えるほどです。 小さな宇宙デブリに関しては、発見・追跡が困難であるため、公開されている以上の宇宙ごみが地球の周辺を漂っていると考えられます。
スペースデブリの発生原因は
スペースデブリが発生する原因ですが、私たちの生活を支える通信衛星や測位衛星などの打ち上げが関係しています。 世界初の人工衛星はロシアによって打ち上げられた「スプートニク1号」です。それから12,000~14,000の人工衛星や探査機が打ち上げられましたが、3割程度が稼働していないと考えられています。 これは燃料切れや故障によるものですが、人工衛星は打ち上げのコストを優先して作られているため、大気圏に再突入できるように設定されていません。
また、スペースシャトルを使って回収するにも、それ自体の打ち上げや回収作業に費用が発生してしまいます。 もちろん、スペースデブリの問題が深刻化し、役目を終えた人工衛星を適切に処分する動きはありますが、中には対策を取られず放置されてしまうもの、制御不能のために回収できないものなど、宇宙空間に残されたままとなってしまうのです。
他にも、人工衛星が打ち上げられる過程で、固定用のバンドや切り離しに使われる爆発ボルト、機器を保護するカバーが放出されます。 さらに小さいものだと、燃焼ガスに含まれる生成物、塗料片などが挙げられるでしょう。 そして、人工衛星とデブリの衝突、実験による破壊行為といったケースも、スペースデブリ発生の大きな原因となっています。
スペースデブリの危険性
スペースデブリの問題は、危険性の高さも注目すべき点です。 放出されたスペースデブリは、秒速7~8キロで移動し続け、これはライフル銃の約10倍のスピードと言えます。
そのため、10センチ程度の小さなデブリであっても、人工衛星や探査機と衝突すれば、完全に破壊されてしまうこともあるのです。 そういった事故が起こると、さらに多くのスペースデブリが発生し、宇宙空間における作業の危険性が増すと言えるでしょう。
関連記事
地球に似ている星が宇宙のどこかに!ハビタブルゾーンとは?
地球は生命に溢れた、奇跡の星だと言われています。そのため、太陽系の中に同じ環境の星は、一つとしてあり
地球は生命に溢れた、奇跡の星だと言われて
スペースデブリは地上に影響はある?
宇宙のごみであるスペースデブリは、地上で暮らす私たちには影響のないものと考えてしまいがちですが、そうとも言い切れません。 なぜなら、スペースデブリが地上に落下する恐れもあるからです。 以前あった地上にスペースデブリが落下したケースを見てみてみましょう。
スカイラブ
スカイラブは1973~1979年の間に地球を周回していた、アメリカが初めて打ち上げた宇宙ステーションです。 地球観測、宇宙開発の基礎なる実験、長時間の無重力環境による実験などに使われましたが、太陽活動の活発化によって大気圏が膨張し空気抵抗が増加した影響で、高度が下がり始めます。
結果、1979年7月11日に大気圏突入。無数の破片に分解されながら、西オーストラリア州に落下しました。 人的な被害はなく、周辺住民や飛行機のパイロットは大きな残骸が大気圏内で分解した際の光跡を目撃し、破片も発見されています。
サリュート7号
サリュート7号は1991年に大気圏へ突入して消滅した、ロシアによる宇宙ステーションです。 ソビエト連邦(当時)は「サリュート計画」として、宇宙に長期滞在するために宇宙ステーションを制作。 その7号機として1982~1986年まで使用されましたが、何度もトラブルが発生し、繰り返し修理が行われました。
1986月8月には無人運用となっていましたが、1990年の太陽活動活性化によって機材が故障、通信が不可能になってしまい、1991年2月7日に制御できない状態のまま、アルゼンチン上空で大気圏突入。 燃え尽きなかった一部の残骸が地上に落ちましたが、こちらも被害は報告されませんでした。
国際宇宙ステーションの宇宙ごみ
2022年は国際宇宙ステーション(ISS)から放出されたごみの一部が、地球に落下。 アメリカ・フロリダ州の民家に直撃しました。
大気圏に突入した際、完全に燃え尽きることなく落下し、重さは0.7キログラムでしたが、民家の屋根と2つの階の天井を突き破っています。 NASAによる調査の結果、貨物パレットにバッテリーを取り付けるための飛行支援装置の支柱だと断定しました。 家の所有者であるアレハンドロ・オテロ氏は「息子が怪我を負うところだった」と語っています。
関連記事
オウムアムアとは?初の恒星間天体は宇宙人の探査機か
2020年、アメリカの国防総省によりUFOらしいものが映った映像が公開され、大きな話題を呼びました。
2020年、アメリカの国防総省によりUF
スペースデブリ削減の取り組みは
最悪の場合、私たちが住む場所に振ってくるかもしれない、危険なスペースデブリですが、何かしらの対策は取られているのでしょうか。
スペースデブリの対策は、主に「監視・観測」「回避・防御」「防止・除去」が挙げられます。 それぞれ、どのような対策が取られているのか確認してみましょう。
監視・観測
スペースデブリによる事故を防ぐため、地球付近で行う観測活動を宇宙状況認識(SSA)と言います。 これは、北アメリカ航空宇宙防衛司令部(NORAD)による宇宙監視ネットワーク(SSN:Space Surveillance Network)、ロシアの宇宙監視システム(SSS:Space Surveilance System)が代表的です。
観測方法は電波を照射するレーダーや、光学望遠鏡が用いられ、約10センチ以上の比較的に大きなデブリはカタログ登録して常に監視。 情報は国際的に共有されます。 日本でも岡山県の美星スペースガードセンター、上斎原スペースガードセンターが有名です。
回避・防御
観測データを基に、スペースデブリを回避する方法もあります。 国際宇宙ステーションでは、10センチ以上スペースデブリであれば、観測によって軌道を予測できるため、衝突の危険があった場合は軌道を変更。回避を行います。 10センチよりも小さいスペースデブリに関しては、観測が困難です。
そのため、ホイップルバンパーという防御材を利用します。 これは、二重の外壁で一層目の板にスペースデブリが衝突した瞬間、その運動エネルギーを熱に変えるものです。 その他にも、搭乗員や機能に致命的な損傷がない設計が施されています。
防止・除去
スペースデブリを発生させないため、国際的なガイドラインも制定されています。 それが、1993年に設立された国際機関間スペースデブリ調整委員会IADC(Inter-Agency Space Debris Coordination Committee)が、2002年に発行した「スペースデブリ軽減のためのガイドライン(Space Debris Mitigation Guidelines)」です。
さらに、国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS:Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)が、これを踏まえて「国連COPUOSスペースデブリ低減ガイドライン(Space Debris Mitigation Guidelines of the COPUOS)」を2007年に制定。 他にも、IADCガイドラインの工業的な実施方法を定めた国際標準「ISO-24113スペースデブリ低減要求」が2010年に制定されています。
スペースデブリの除去に関しても、さまざまな技術があり、それをActive Debris Removal(ADR)と呼びます。 ネットでデブリを捕獲する、ロボットアームで捕獲する、ドッキングして一緒に大気圏へ突入するといった方法が開発されていますが、どれも高度な技術が必要です。 技術だけでなく、コストの問題もあり、実用化には時間がかかりますが、今後の開発が期待されています。
関連記事
なぜ地球だけに生命が誕生したの?条件や奇跡の数々とは
地球が奇跡の星、と言われるのは、広い宇宙の中に、これだけ多くの生命が存在している星がないからでしょう
地球が奇跡の星、と言われるのは、広い宇宙
地上も宇宙もごみ問題は深刻
このように、宇宙はごみによる問題は危険をもたらしていますが、その原因は人間によるものです。 そして、それは地球上でも同じことが言えます。
私たちが出したごみが自然に影響を及ぼし、多くの環境問題を生み出しているのです。 宇宙でも地球でも、ごみが残らないよう心掛けなければなりません。 身近なリサイクルを意識する、環境に悪い習慣は避けるなど、簡単なことから始めてみてください。
関連記事
ゴミ問題による自然・環境問題へ影響は?3Rを意識しよう
文明や経済が発展したことで、人間の暮らしは便利で豊かなものになりました。 しかし、その裏側では大量
文明や経済が発展したことで、人間の暮らし