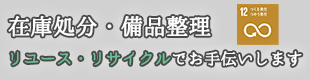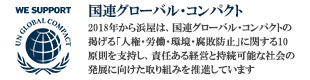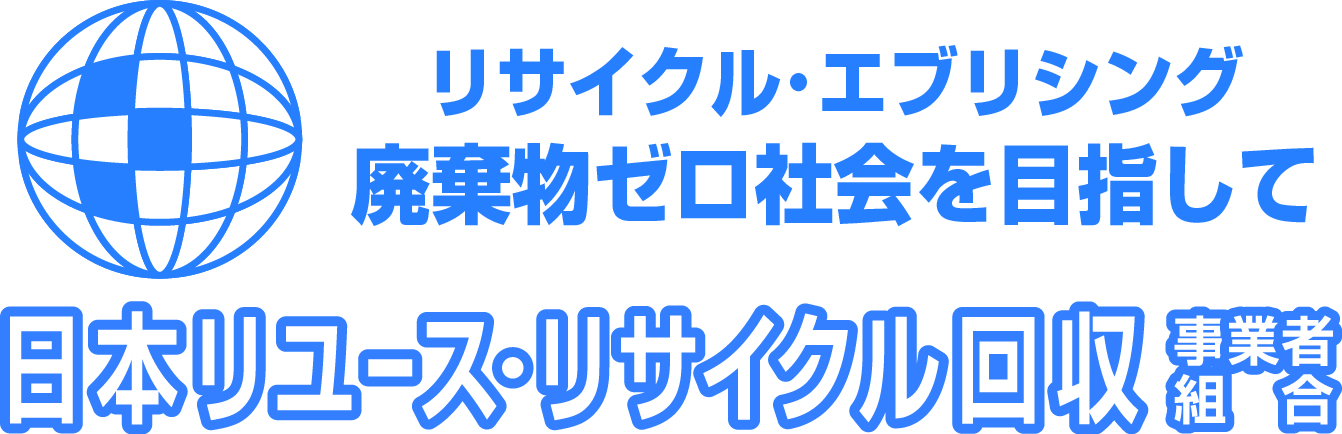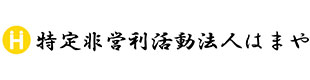桜が温暖化の影響で咲かなくなる?開花が遅い原因とは

桜は日本の原風景の1つとも言える存在で、春の開花を楽しみに待っている人も多いはずです。 しかし、そんな桜が温暖化の進行によって、咲かなくなる恐れがあることをご存じでしょうか。
今回は桜にもたらす温暖化の影響を解説します。 また、温暖化の他にも桜の風景を奪うかもしれない環境問題もご紹介します。
温暖化により桜の開花が早まる?
桜と言えば入学式など新生活が始まるタイミングで満開になるイメージを抱くかもしれませんが、それが温暖化の進行によって変化しつつあります。 気象庁はさくらの開花日を毎年公開していますが、それを見ると時期の変化は一目瞭然です。
例えば東京の場合、2000年までは3月下旬から4月以降の開花となりますが、2001年以降は3月中旬から下旬となっています。
| 西暦 | 開花日 | 西暦 | 開花日 |
|---|---|---|---|
| 1981 | 3月26日 | 1991 | 3月30日 |
| 1982 | 3月23日 | 1992 | 3月24日 |
| 1983 | 3月31日 | 1993 | 3月24日 |
| 1984 | 4月11日 | 1994 | 3月31日 |
| 1985 | 4月3日 | 1995 | 3月31日 |
| 1986 | 4月3日 | 1996 | 3月31日 |
| 1987 | 3月23日 | 1997 | 3月21日 |
| 1988 | 4月2日 | 1998 | 3月27日 |
| 1989 | 3月20日 | 1999 | 3月24日 |
| 1990 | 3月20日 | 2000 | 3月30日 |
| 西暦 | 開花日 | 西暦 | 開花日 | 西暦 | 開花日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3月23日 | 2011 | 3月28日 | 2021 | 3月14日 |
| 2002 | 3月16日 | 2012 | 3月31日 | 2022 | 3月20日 |
| 2003 | 3月27日 | 2013 | 3月16日 | 2023 | 3月19日 |
| 2004 | 3月18日 | 2014 | 3月25日 | 2024 | 3月29日 |
| 2005 | 3月31日 | 2015 | 3月23日 | ||
| 2006 | 3月21日 | 2016 | 3月21日 | ||
| 2007 | 3月20日 | 2017 | 3月21日 | ||
| 2008 | 3月22日 | 2018 | 3月17日 | ||
| 2009 | 3月21日 | 2019 | 3月21日 | ||
| 2010 | 3月22日 | 2020 | 3月14日 |
参考:気象庁 さくらの開花日
2~3年で見ると些細な変化ですが、10年や20年の単位で見ると大きな変化であることは間違いありません。 また、温暖化が進めば進むほど開花時期が遅くなるだけでなく、このままでは桜そのものが咲かなくなる恐れがあります。 実際、奄美大島以南は日本の代表的な桜であるソメイヨシノの育成に適さない環境です。
つまり、このまま温暖化が進行すれば、桜の育成に適さない範囲が徐々に北上し、いつかは日本では咲かなくなると考えられるのです。
関連記事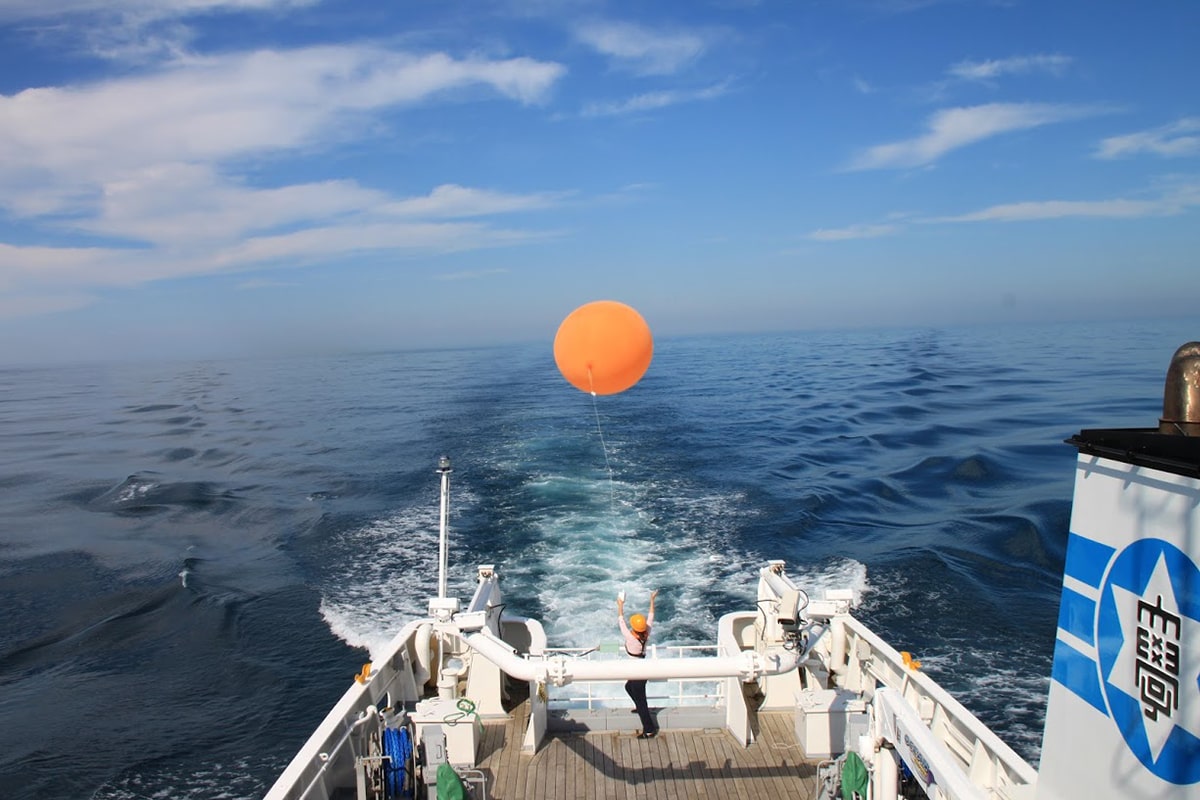
暑い夏が続くと思ったら急に冬がやってくる 日本は四季から二季に変わったのか 専門家が語る異常気象 立花義裕教授インタビュー
ここ数年は延々と猛暑が続くと思ったら急激に寒くなる、といった温度の落差が激しく、驚いている人も少なく
ここ数年は延々と猛暑が続くと思ったら急激
温暖化によって桜が咲かなくなる理由
なぜ、温暖化によって気温が高くなると、桜の開花時期の遅れや咲かなくなるといった事態になってしまうのでしょうか。 桜は暖かくなれば咲く、というシンプルなものではなく、冬の寒さも必要となります。 桜が咲く仕組みをもう少し詳しく見てみましょう。
まず、桜は夏になると、次の春に花を咲かせるため、花芽を形成します。 この花芽は夏から秋にかけて成長しますが、冬の間は必要なエネルギーを蓄えるために休眠状態へ。 ただ、数十日ほど冬の寒さにさらされると、今度は眠りから覚めます。
これを「休眠打破」と言って、一般的に5℃程度の低温刺激を受けることによって目覚める現象です。 目覚めた後は、開花に向けて成長を再開。私たちが美しいと感じる状態まで成長します。
しかし、温暖化によって冬の気温が上昇してしまうと、休眠打破が正常に行われません。 結果、桜が咲かなくなる未来も考えられるのです。
関連記事
日本五大桜とは?所在地から各々の特徴をご紹介!
少しずつ寒い冬から、春の温かな気配を感じられる時期になってきました。 春の訪れによって期待して
少しずつ寒い冬から、春の温かな気配を感じ
温暖化だけじゃない!桜が失われる原因とは
また、桜が日本で咲かなくなる原因は、温暖化だけではありません。温暖化の他に考えられる、桜の脅威もご紹介します。
外来生物による食害
2012年、中国や朝鮮半島由来の昆虫、クビアカツヤカミキリが愛知県で初めて発見されました。 この昆虫は桜の天敵と言われ、樹木に寄生して枯死させるとった特徴があります。 特にソメイヨシノは被害が多く、環境省によって2018年からクビアカツヤカミキリは特定外来種に指定されました。
また、クビアカツヤカミキリは繁殖力が強く、1匹のメスが300~1000個の卵を産み、2019年には奈良県や三重県、和歌山県で確認されるなど、その分布が広がりつつあります。
関連記事
外来種による深刻な問題!どんな悪影響があるのか?
いま日本に存在している様々な野生動物が危機に晒されています。 その危機をもたらすのは、外来種と
いま日本に存在している様々な野生動物が危
都市化の影響
ソメイヨシノなどの桜は、都市部に街路樹として植えられることも少なくありません。 しかし、街路樹は建設物の陰に隠れることで十分な光が得られず、さらには根の近くまで舗装されて酸素と水の供給が滞ってしまう、という問題があります。
他にも排気ガスの影響や花見の客に枝を折られるといったことが原因で、健全に桜が育たないケースも見られます。
関連記事
都市化による問題とは?どのような影響があるのか
都市化、と言われるように、農村や地方の人口が少なくなりつつあります。 流行の先端や仕事の選択肢
都市化、と言われるように、農村や地方の人
菌類による被害
ソメイヨシノは「てんぐ巣病」に弱いという性質があります。 これは感染すると異常に多くの細い枝が密生し、まるで鳥の巣のように見えることから「てんぐ巣」と呼ばれる植物病害で、その原因は菌類やウイルスと考えられています。 てんぐ巣病にかかると、花が咲かなくなる、光合成の効率が低下して育ちが悪くなるなどの影響があり、周囲の桜に感染が広がることも。
他にも、コフキサルノコシカケやナラタケモドキの感染によって桜が衰えるケースも見られ、対策と観察の強化が呼びかけられています。
桜が失われないために私たちができることは?
このように、温暖化現象を始めとする環境問題は美しい自然を奪ってしまう恐れがあります。 しかし、環境問題の多くは人間が原因です。
桜が失われないためにも、環境問題のためにできることを意識するなど、個人で取り組める対策はありますが、現状を知って多くの人に伝えるというアクションも大切だと言えます。 ぜひ、エコトピアを通して環境問題を知り、多くの人に伝えることを試してみてください。
関連記事
地球の環境問題とは?代表的な現象と私たちにできること
地球ではさまざまな環境問題が起こり、人間を含む多くの生命が危機に晒されています。 この地球で起
地球ではさまざまな環境問題が起こり、人間